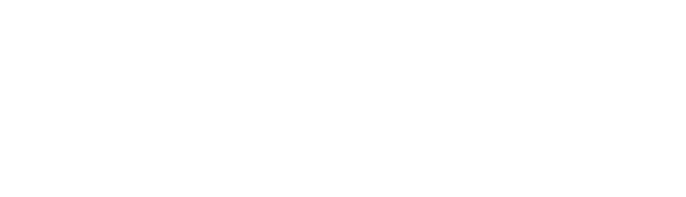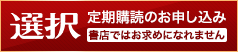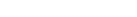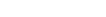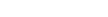雑誌を殺す裁判所
名誉毀損訴訟という「言論弾圧」
2011年3月号公開
相撲に八百長があるなんて当たり前じゃないか―。警察リークによって発覚して一大騒動となっている大相撲の八百長問題を、そんなふうに覚めて眺めるのも一つの見識ではあろう。
ただ、今回の騒動には断じて見過ごせぬ問題も潜む。日本相撲協会による厚顔無恥な恫喝的メディア訴訟と、それに易々と応じた司法権の砦=裁判所の無知不見識だ。いや、真に悪質なのは裁判所かもしれない。闊達なメディア報道を窒息させかねぬ愚に突き進んできたのは裁判所だからである。
「週刊現代」(講談社)が二〇〇七年に八百長問題を連続追及し、相撲協会が名誉毀損で提訴したのは周知の通り。原告には当時の横綱・朝青龍らが名を連ね、賠償請求総額は実に七億円超に上った。東京地裁は〇九年三月二十六日、講談社側に計四千二百九十万円の賠償を命じた。原告が複数とはいえ、一件の名誉毀損判決としては前代未聞の高額賠償として驚きを広げた。最終的に昨年十月に四千万円超の賠償命令が確定している。
雑誌を「狙い撃ち」
ある大手紙の司法担当デスクは「週刊誌の取材に杜撰なところがあったのは否めない」と語るが、今となれば噴飯物の判決としかいえない。講談社幹部はこう憤る。
「公判では、今回の騒動で八百長を認めた力士まで『八百長など絶対ない』という陳述書を提出し、賠償金の一部を受け取っている。こんなバカげた裁判を許せばメディアは何も書けない」
この件は講談社が相撲協会を逆に刑事告訴する動きを見せ、当の「週刊現代」も勢い込んで記事にしているから、ここでは詳述しない。問題は、なぜこれほど図々しい訴訟が罷り通り、裁判所も超高額賠償で応じたのか、という点だ。
話は約十年前に遡る。最高裁の付設機関である司法研修所が〇一年、メディアによる「名誉毀損」に関する「慰謝料額の算定基準」なるものを策定した。背後で蠢いたのは政治の圧力である。別の大手紙司法担当記者が振り返る。
「自民党は九〇年代末からメディアの政権批判に憤懣を募らせていたが、特に当時の森喜朗政権はメディアの総叩きを浴び、不満は頂点に達していた。また、一部週刊誌の創価学会批判に苛立った公明党も盛んに声を上げた。これを受けて裁判所が名誉毀損の賠償額を一挙に引き上げる動きに出た」
自民、公明などの連立だった森政権が首相自身の軽率発言などで強い批判を浴び、支持率低迷に喘いだのは記憶に新しい。公明党も九〇年代末から池田大作名誉会長のスキャンダル等を一部週刊誌に書き立てられていた。
当時の与党・自民、公明が裁判所を突き上げたのは国会論戦からも浮かび上がる。例えば法相だった自民党の高村正彦氏は〇一年三月の参院法務委員会で「マスコミの名誉毀損で泣き寝入りしている人たちがたくさんいる」となじり、公明党議員も口々にこう訴えた。
「名誉侵害の損害賠償額を引き上げるべきだと声を大にして申し上げたい」(沢たまき議員〈故人〉、同月の参院予算委員会)
「損害賠償額が低調過ぎる」「懲罰的な損害賠償も考えられていけばいい」(魚住裕一郎議員、同年五月の参院法務委員会)
そして五月十六日の衆院法務委員会では当時の冬柴鐵三・公明党幹事長が大々的にこの問題を取り上げて「賠償額引き上げ」を迫り、最高裁民事局長がこう答弁した。
「名誉毀損の損害賠償額が低いという意見は承知しており、司法研修所で適切な算定も検討します」
こうしてつくられたのが前述の「基準」であり、前後して名誉毀損訴訟の賠償額は一気に高騰する。〇一年三月は巨人選手の醜聞を報じた「週刊ポスト」(小学館)に東京地裁が一千万円、同年十月には著名建築家の建築を批判した「週刊文春」(文藝春秋)にやはり東京地裁が一千万円の賠償を命じ、以後、高額賠償判決は各地の裁判所で相次いだ。一例を別表に掲げる。
相撲協会をめぐる高額賠償判決はこの一つの頂点といえるのだが、標的とされたのが雑誌メディアばかりであることに留意してほしい。前出の司法担当記者が言う。
「雑誌の取材が新聞などより甘いこともあるでしょうが、新聞やテレビは良く言えば慎重、悪く言えば臆病で、政治家や財界人、著名人に関する果敢な報道に手を付けない。政治家などの側から見れば、新聞やテレビは記者クラブや許認可権を通じて抑えが利くが、雑誌は抑えが利きにくく、やんちゃにスキャンダルを書きまくる。賠償高額化は最初から雑誌を狙い撃ちするものだったから、思惑通りということでしょう」
でたらめな「算定基準」
もちろん、杜撰な取材で書き飛ばした記事など論外だが、記者クラブなどで飼い馴らされがちな新聞やテレビに対し、雑誌メディアが果敢な報道でタブーに風穴を開けてきたのは間違いない。事実、近年の政治家スキャンダルなどは多くが雑誌のスクープが発端だ。
だが、賠償高額化はそんな雑誌メディアを窒息させつつある。大手週刊誌の元編集長もこう嘆く。
「出版不況の中、高額賠償まで命じられたら苦しく、どうしても弱腰になる。もっと問題なのは、こうした傾向に乗じて財界人や著名人が常軌を逸した高額請求訴訟を吹っかけてくること」
確かに最近、そうした例は目立つ。例えば〇七年にはキヤノンの御手洗冨士夫会長が「週刊現代」記事に二億円の賠償を求める訴訟を起こした。一〇年六月にはアイドルグループAKB48のマネジメント会社が「週刊文春」記事に一億五千万円の賠償を求める訴訟を起こしている。同元編集長の話。
「裁判所は徹底して雑誌に冷たいし、情報源を明かせない我々は圧倒的に不利。御手洗氏のケースなどは記事内容に全く問題はなく、最終的に『週刊現代』側が勝ちましたが、それでも一審では重箱の隅をつつくような理由で二百万円の賠償を命じられています」
さらに大問題なのは、前述した「基準」の中身だ。相次ぐ高額賠償はこれに基づくものだが、点数制で名誉毀損の「悪質性」を算出するという同基準は、政治家やタレントなど「公人」に類すべき人物ほど賠償額を高く設定している。
今さら記すまでもなく、メディアが果たすべき最重要使命は権力監視である。その対象は公的組織や政治家、財界人は言うに及ばず、大きな社会的影響力を持つ「公人」にこそ向けられねばならない。にもかかわらず、最高裁基準は「公人」ほど厚く庇護するという天地が転倒した内容となっているのだ。
これほど馬鹿げた「基準」を司法がつくって賠償額を高騰させたからこそ、強者による恫喝的訴訟が横行し、果ては相撲協会の如き恥知らずの訴えが起きたのだ。このようなことが続けば、雑誌メディアは死に絶え、お行儀のいい「官製メディア」ばかりが生き残る。
掲載物の無断転載・複製を禁じます©選択出版