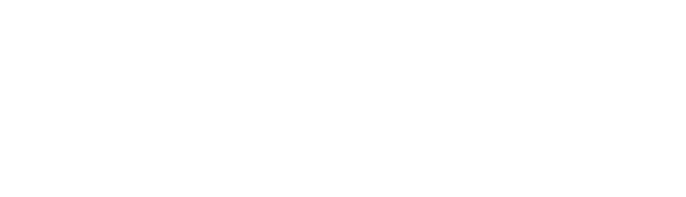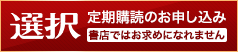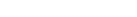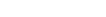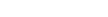本に遇う 連載150
やがて悲しき調査報道
河谷史夫
2012年6月号公開
新聞と新聞記者への批判が強い。評判の悪さは今に始まったことではないが、去年の「三・一一」以来、目立って悪くなってきていないか。現役のなかには、「大震災以後、新聞の信頼は上がっていますよ」と楽天的な輩もあるが、読者の見方はそんなに甘くはない。
「新聞は本当のことを書いているのか」という評言が、わたしのようにすでに世間とはほとんど没交渉で、ただ本と酒と、ついでに医者巡りに日を消すのみの隠居暮らしにも聞こえてくる。要するに新聞記事は「大本営発表」ではないか、と問うているのである。
戦前戦中、新聞は大本営の発表を垂れ流した。敵に与えた攻撃効果を過大に見積もり、自軍の損傷は過小に数え、撤退を転進と言い、全滅を玉砕と飾った。伸びきった戦線のあちこちで、すでに壊滅的敗走が始まっているのにその実相を伝えず、国民を欺いた。
戦後の新聞は、その反省から出発したのであった。
それなのに、例えば福島原発事故をめぐる記事が「大本営発表」に比せられるとすれば由々しき事態と言わねばならない。戦前は国家の言論統制があったから仕方なかったという言い訳ができた。検閲など今はない。だのに当局発表のままかと目されては万事休すではないか。新聞に求められているのは政府や東京電力が秘密にしている事実を暴くことだ。すなわち調査報道に徹することである。
朝日新聞社会部でリクルート事件や談合キャンペーンなど調査報道の数々を手がけ、「新聞界にその人あり」と知られた山本博は、調査報道を「ニュースソースを当局に頼らず、放っておけば将来にわたっても公表されないだろう当局にとって都合の悪い、隠しておきたい事実を、ジャーナリズムが直接、調査取材し、自らの責任で明るみに出すこと」と定義した。
要約すれば、それは「公権力の監視」ということである。つまり、「公権力の隠れた疑惑、腐敗、ウソなどをジャーナリズムが自らの責任で調査し、国民の知る権利に応える行為」ということだ。
遺憾ながら山本の後に山本なしで、朝日ではリクルート事件以後、調査報道の伝統は長らく途絶えた。しかし種が風に乗って飛び、どこかで芽を吹くように、高知新聞、北海道新聞と警察の裏金づくりを明るみに引き出す調査報道が近年相次いだ。新聞見物人のわたしとしては、新聞の存在理由が再認識されてよかったと思っていた。
新聞には二種類ある。面白い新聞と面白くない新聞と。発表ものばかりの新聞が面白いわけはない。面白い新聞とは、独自の調査報道に満ちている新聞である。警察裏金を追及する高知新聞や道新は連日きっと面白かったろう。
ところが高田昌幸著『真実 新聞が警察に跪いた日』を読んで愕然とした。これは一体どうしたことか、なぜこんなことになるのか。
二〇〇三年晩秋に始まった道新による北海道警の裏金問題追及は、全国紙のだらしなさを尻目に見事なものであった。高田は報道本部デスクとして取材指揮を執った。テレビに抜かれた発端から、実名の内部告発者が現れて、組織ぐるみの不正があぶり出される経緯は、すでに刊行されている『追及・北海道警「裏金」疑惑』に詳しい。
高田の新著は、「追及その後」を記録したものである。新聞協会賞、日本ジャーナリスト会議大賞、菊池寛賞の三賞を受けた道新の取材班は、思いも寄らぬ反動に見舞われる。その挙句、高田は二十五年間勤めた道新を辞めるのである。
高田は基本方針を三つ掲げた。?道警に裏金づくりの実態を認めさせる?取材には道警担当記者が当たる?問題を一道警の問題に終わらせない、の三つである。方針どおりに突き進むのだが、とりわけ?に高田の理念が出ている。
こういう取材は遊軍が班を作って当たるのが「常識」であり、記者クラブ常駐記者は外れる。日ごろ材料をもらう相手に「あなたは不正をしていますか」と聞くわけにはいくまいからだ。そこを高田は「記者クラブに常駐するのは権力監視のためなのだ」という信条に立って、これを貫く。
だが赫々たる成果を挙げた取材班を、社外と社内と二方向から、想像を絶する逆流の波が襲った。
最初は些細に見えた。元道警総務部長―巡査から警視長にまで立身した男が、取材班が出した本に引用されている自分の発言を否定し、これを「捏造」と断じて訂正と謝罪を要求して来た。じくじくと執拗だったが、高田らは大事になるとは思いもしなかった。
〇五年三月、道新が打った「麻薬捜査の失敗」を暴露する特ダネを道警が全面否定して局面が転換する。道警は道新に記事の削除を要求。これが元総務部長による抗議に連動して、「道新は捏造体質」といった大攻撃が強まるのである。
外からの動きに呼応して、社内に取材班を貶めようとする策謀の波が起きる。やっかみやそねみは新聞社にも珍しくないから驚くことはない。驚くべきことは、誰も知らないところで道新幹部と道警側との秘密交渉が繰り返されていたことだ。信じ難いが手打ちの条件まで話されていた。広告局社員の金銭不祥事が発覚して、道新経営陣は道警との友好関係を取り戻したい一心にかられていたのだ。
元総務部長は高田らを名誉毀損で提訴。道警も「けじめをつけろ」と言い続ける。「けじめ」とは「情報源を明かせ」ということだった。連中はまだ「道新のネタ元」を知らない。突き止めるのに躍起なのだと気づいたとき、この勝負は負けるかも知れないと高田は観念した。「情報源は絶対に言えない」とすれば、敗訴になるだろう。
社内では「査問」まで開かれた。高田らは再三「情報源」を質される。言えば道警に筒抜けになるからと拒否したが、社長の意向を受けての査問だったと知って、高田は道新に見切りをつける。
腰の据わらない経営陣というのはどうしようもないものだ。
「おもしろうてやがて悲しき……」と芭蕉は鵜飼を詠んだが、道新の調査報道はさながら鵜飼のように終わったのであった。
(敬称略)
「新聞は本当のことを書いているのか」という評言が、わたしのようにすでに世間とはほとんど没交渉で、ただ本と酒と、ついでに医者巡りに日を消すのみの隠居暮らしにも聞こえてくる。要するに新聞記事は「大本営発表」ではないか、と問うているのである。
戦前戦中、新聞は大本営の発表を垂れ流した。敵に与えた攻撃効果を過大に見積もり、自軍の損傷は過小に数え、撤退を転進と言い、全滅を玉砕と飾った。伸びきった戦線のあちこちで、すでに壊滅的敗走が始まっているのにその実相を伝えず、国民を欺いた。
戦後の新聞は、その反省から出発したのであった。
それなのに、例えば福島原発事故をめぐる記事が「大本営発表」に比せられるとすれば由々しき事態と言わねばならない。戦前は国家の言論統制があったから仕方なかったという言い訳ができた。検閲など今はない。だのに当局発表のままかと目されては万事休すではないか。新聞に求められているのは政府や東京電力が秘密にしている事実を暴くことだ。すなわち調査報道に徹することである。
朝日新聞社会部でリクルート事件や談合キャンペーンなど調査報道の数々を手がけ、「新聞界にその人あり」と知られた山本博は、調査報道を「ニュースソースを当局に頼らず、放っておけば将来にわたっても公表されないだろう当局にとって都合の悪い、隠しておきたい事実を、ジャーナリズムが直接、調査取材し、自らの責任で明るみに出すこと」と定義した。
要約すれば、それは「公権力の監視」ということである。つまり、「公権力の隠れた疑惑、腐敗、ウソなどをジャーナリズムが自らの責任で調査し、国民の知る権利に応える行為」ということだ。
遺憾ながら山本の後に山本なしで、朝日ではリクルート事件以後、調査報道の伝統は長らく途絶えた。しかし種が風に乗って飛び、どこかで芽を吹くように、高知新聞、北海道新聞と警察の裏金づくりを明るみに引き出す調査報道が近年相次いだ。新聞見物人のわたしとしては、新聞の存在理由が再認識されてよかったと思っていた。
新聞には二種類ある。面白い新聞と面白くない新聞と。発表ものばかりの新聞が面白いわけはない。面白い新聞とは、独自の調査報道に満ちている新聞である。警察裏金を追及する高知新聞や道新は連日きっと面白かったろう。
ところが高田昌幸著『真実 新聞が警察に跪いた日』を読んで愕然とした。これは一体どうしたことか、なぜこんなことになるのか。
二〇〇三年晩秋に始まった道新による北海道警の裏金問題追及は、全国紙のだらしなさを尻目に見事なものであった。高田は報道本部デスクとして取材指揮を執った。テレビに抜かれた発端から、実名の内部告発者が現れて、組織ぐるみの不正があぶり出される経緯は、すでに刊行されている『追及・北海道警「裏金」疑惑』に詳しい。
高田の新著は、「追及その後」を記録したものである。新聞協会賞、日本ジャーナリスト会議大賞、菊池寛賞の三賞を受けた道新の取材班は、思いも寄らぬ反動に見舞われる。その挙句、高田は二十五年間勤めた道新を辞めるのである。
高田は基本方針を三つ掲げた。?道警に裏金づくりの実態を認めさせる?取材には道警担当記者が当たる?問題を一道警の問題に終わらせない、の三つである。方針どおりに突き進むのだが、とりわけ?に高田の理念が出ている。
こういう取材は遊軍が班を作って当たるのが「常識」であり、記者クラブ常駐記者は外れる。日ごろ材料をもらう相手に「あなたは不正をしていますか」と聞くわけにはいくまいからだ。そこを高田は「記者クラブに常駐するのは権力監視のためなのだ」という信条に立って、これを貫く。
だが赫々たる成果を挙げた取材班を、社外と社内と二方向から、想像を絶する逆流の波が襲った。
最初は些細に見えた。元道警総務部長―巡査から警視長にまで立身した男が、取材班が出した本に引用されている自分の発言を否定し、これを「捏造」と断じて訂正と謝罪を要求して来た。じくじくと執拗だったが、高田らは大事になるとは思いもしなかった。
〇五年三月、道新が打った「麻薬捜査の失敗」を暴露する特ダネを道警が全面否定して局面が転換する。道警は道新に記事の削除を要求。これが元総務部長による抗議に連動して、「道新は捏造体質」といった大攻撃が強まるのである。
外からの動きに呼応して、社内に取材班を貶めようとする策謀の波が起きる。やっかみやそねみは新聞社にも珍しくないから驚くことはない。驚くべきことは、誰も知らないところで道新幹部と道警側との秘密交渉が繰り返されていたことだ。信じ難いが手打ちの条件まで話されていた。広告局社員の金銭不祥事が発覚して、道新経営陣は道警との友好関係を取り戻したい一心にかられていたのだ。
元総務部長は高田らを名誉毀損で提訴。道警も「けじめをつけろ」と言い続ける。「けじめ」とは「情報源を明かせ」ということだった。連中はまだ「道新のネタ元」を知らない。突き止めるのに躍起なのだと気づいたとき、この勝負は負けるかも知れないと高田は観念した。「情報源は絶対に言えない」とすれば、敗訴になるだろう。
社内では「査問」まで開かれた。高田らは再三「情報源」を質される。言えば道警に筒抜けになるからと拒否したが、社長の意向を受けての査問だったと知って、高田は道新に見切りをつける。
腰の据わらない経営陣というのはどうしようもないものだ。
「おもしろうてやがて悲しき……」と芭蕉は鵜飼を詠んだが、道新の調査報道はさながら鵜飼のように終わったのであった。
(敬称略)
掲載物の無断転載・複製を禁じます©選択出版