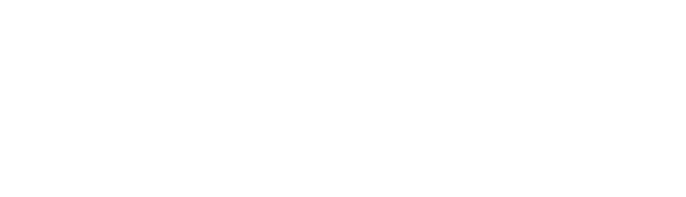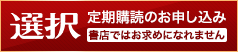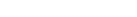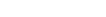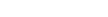日本郵船に「融資詐欺」共謀疑惑
倒産した船主会社との「黒い蜜月」
2016年2月号公開
「日本郵船に騙された」。取引金融機関の間ではこんな穏やかならざる囁きも交わされているという。
〝事件〟は昨年十一月十一日、ある船主会社グループの経営破綻劇で幕を開けた。統括会社で船舶関連の契約業務請負や管理業務を行っているラムスコーポレーション(東京・港区)と実際に船舶を所有している三十八社のSPC(特別目的会社)から成るユナイテッドオーシャン・グループ(UOG)―その借入金の一部に債務不履行(デフォルト)が発生し、債権者の一人だったみずほフィナンシャルグループ系のリース準大手、興銀リースから会社更生法の適用申請を申し立てられたのだ。
UOGとラムス社は新船建造費の融資を受けるに際し、金融機関との間でクロスデフォルト条項を交わしていたとされている。借入金が一つでもデフォルトを起こせば、残りの借入金が返済期限を迎えていなくても、すべてがデフォルトを起こしたとみなされ、債権者が返済を要求できる仕組み。興銀リースはその発動に踏み切ったのだ。
そして同十二月三十一日、UOGは東京地裁から会社更生法手続き開始の決定を受ける。興銀リース自体の焦げ付きは三十七億円弱に過ぎなかったものの、グループ全体での負債総額は約一千四百億円にも上った。規模としては昨年で最大級の企業倒産だった。
とはいえ、ここまでなら規模こそ大きいものの、それこそ「どこにでもある破綻劇」(金融筋)。すでに更生法の手続き開始が決まった以上、その枠組みに沿って清々粛々と法的整理を進めていけば済む。
ところが―事はこれでは終わらなかったのである。倒産と相前後する形で、UOGが偽りの契約内容をもとに金融機関から不正に融資を引き出していた疑いが浮上したうえ、日本郵船がどうやらそれに一枚嚙んでいるのでは、といった疑惑までが銀行関係者らの間でまことしやかに取り沙汰されはじめたからだ。
「クルマも女もあてがった」
実はUOGは「極めて特殊な船主会社」(海運業界筋)だとされている。シンガポールに二十四社、パナマに十四社登記されているSPCを通じて、七万トン以上のパナマックス船十三隻、四万トン以上のハンディマックス船九隻、自動車船七隻など三十八隻を保有しているが、そのすべてを日本郵船一社だけに貸し付けているためだ。
通常三十八隻もの船を所有していれば、複数の海運会社に船を貸して、リスク分散を図るのが真っ当な経営の在り方だ。海運会社が破綻すれば傭船料を取りっぱぐれる恐れもあるからだ。実際、昨年九月末には売上高で業界五位の第一中央汽船が民事再生法の適用を申請するなど、直近での破綻劇も起こっている。
一方で、船主からすれば日本郵船のような相対的に財務体質の良好な海運会社とできるだけ多くの取引関係を持ちたいと思うのも本音だろう。それだけに同社をめぐる船主間の貸し付け競争は激しい。とりわけ二〇一二年以降は、海運市況や船価が底に達したとみたファンドなど世界の投機マネーが大量に造船市場に流入、競争はさらにエスカレートしている。それなのに「なぜUOGがここまで日本郵船に食い込めたのか」。海運大手三社の一角、商船三井幹部の一人もしきりと首を捻る。
UOGはインド人のヴィパン・クマール・シャルマ社長が一代で起こした会社だ。十歳のときから日本で育った人物で、一九九一年に設立した。日本郵船との間に無論、何の資本関係もない。それが日本郵船の全傭船隻数五百十四隻(一五年九月末)の七・四%を占めるまでに取引を拡大させたのだ。
業界関係者によると、シャルマ社長による日本郵船首脳や幹部らに対する〝接待攻勢〟は「実はそのスジでは有名な話だった」という。一説では経営陣や役員候補の人材に対し、社長自身が「相当なカネを使った。クルマも女もあてがった」などと吹聴していたとか。なかでも経団連副会長をつとめ、「最高実力者」(日本郵船関係者)とされた草刈隆郎元社長・会長(現特別顧問)とは「因縁浅からぬものがあった」(周辺筋)とされている。
だが、それならばどうしてUOGは破綻しなければならなかったのか。船主会社は取引相手の海運会社が存続している限り、安定・継続的に傭船料が入ってくるストックビジネスだ。本業に専念してさえいれば「大儲けはできないにしても、借入金の返済に行き詰まるほど資金繰りに窮するようなことはほとんどない」(メガバンク筋)ともいわれている。まして傭船先は大手三社のなかでも信用格付け最高位の日本郵船だ。
一般的に船主が新船を建造しようとする場合、その資金は総工費の一割を自己資金、残り九割を金融機関からの借り入れで賄うといわれている。しかし、金融機関側からすれば建造する船の傭船先が決まっており、その傭船契約の内容が確かなものでなければ危なっかしくて多額の融資など実行できるハズもない。
そこで金融機関側は融資に際して、建造される船がどこに貸し出されて、どれくらいの傭船料が見込めるのかを確認することになる。そのうえで傭船契約から得られる傭船料が元利金の返済原資となるようスキームを設計し、ファイナンスを実施するわけだ。「傭船料債権譲渡担保」と呼ばれる仕組みで、逆に船主側からすれば、傭船先から得られる傭船料の中から金融機関に対して決められた契約の通りに借入金の返済を行っていけば自ずと完済にまでこぎつけられることになる。デフォルトを起こすリスクは極めて少ない。なのに―UOGは破綻した。
初歩的ともいえる〝融資詐欺〟
こうして浮かび上がってきたのが、前述の疑惑だ。要するにUOGが起こすハズのないデフォルトを起こしたのは「そもそもUOGが金融機関に提出した傭船契約書そのものに何らかの瑕疵があったか、意図的に細工が施されたシロモノだったのではないか」(銀行筋)というわけだ。
そんななか業界関係者らの間で駆け巡っているのが、UOGと日本郵船との間の傭船料の取り決めは「異例ともいえる内容だった」との情報だ。当初の傭船料は固定だが、数年後には変動制に移行し、「国際的な海運市況に連動させる形になっていた」というのである。
事実とすれば業界の商慣行や常識から言って「あり得ない契約」(川崎汽船関係者)だろう。運賃相場の高止まりや上昇が続くのなら、確かに船主にとって変動制は好都合だ。しかし、ひとたび下落に転じれば傭船料収入が急減、金融機関への返済が滞り、あっという間に破綻に追い込まれるのは「火を見るより明らか」(メガバンク幹部)だからだ。
第一、こうした契約内容では回収不能リスクが高過ぎて、金融機関も融資自体を行わないし、行えない。強行して損失が生じれば「背任容疑で刑事責任すら問われかねない」(同前)ためだ。しかし現実には、UOGへの融資は実行された。だとすれば考えられるのは、UOGが市況連動型傭船料という事実をひた隠しにしていたか、契約書を完全固定制に偽造していたかということくらいしかあるまい。
金融関係者によるとシップファイナンスの場合、借り入れを希望する船主が提出する契約書類は必ずしも原本である必要はなく、コピーで十分なのだという。そこでこれを悪用する形で紛い物を作成、本物に見せかけて銀行側に提出していたのではないか――。大手銀行のある幹部はこう推察する。
典型的で初歩的ともいえる“融資詐欺”だが、金融機関側からすれば提出された書類の真贋はともあれ、契約書に記載され、傭船料収入ひいては借入金返済原資の裏付けともなっている「日本郵船」の肩書と信用力は絶対的にモノを言う。「資金需要の伸び悩みに困っていただけに、一も二もなく融資に応じたのでは……」。大手地銀幹部は思いを巡らせる。
何かしらの作為とある種の不実
それにしても日本郵船は「非常識」とされている傭船料市況スライドの契約をなぜUOGに押し付けたのだろう。船主会社と海運会社の力関係を利用した、いわば優越的地位の乱用といえなくもないが、こうした契約内容ではUOGが金融機関から新船建造のための融資を引き出せないであろうことは「日本郵船側も当然、認識していたハズだ」(海運業界関係者)。
だとすれば、それでもなお融資を引き出そうとするとUOGが、何らかの不正に手を染めざるを得なくなる可能性も「当然ながら予見できたハズ」(業界筋)。にもかかわらず、日本郵船は目をつぶっていたばかりか、実際に融資が引き出されて三十八隻もの船が建造されるに至るまでひたすら沈黙を続けた。「そこに何かしらの作為とある種の不実を感じざるを得ない」。金融関係者の一人は呟く。騙された―の声が燻る所以か。
UOGが興銀リース以外のどんな金融機関とどれくらいの規模の取引があったのか、現時点ではすべてが具体的に明確になっているわけではない。しかし各大手銀行ともここ数年揃ってシップファイナンスに力を入れてきた経緯もあるだけに、その大半が今回の破綻に巻き込まれたのはほぼ確実。事情通らの間では「みずほ銀行や商工中金、さらには日本郵船本体のメーンバンクでもある三菱東京UFJ銀行なども焦げ付きを抱えたらしい」といった観測が飛び交う。また、りそなホールディングスが二〇一五年度上期(四~九月)決算で大幅な減益に転じる原因となった約三百二十二億円の個別貸倒引当金の計上も「その大部分がUOG向けだった」(市場関係者)とも取り沙汰されている。
日本郵船ではUOGの破綻後も同社との傭船契約を解除せず、現行契約の残存期間中はそのまま船を借りて傭船料を支払い続けていくことで、ひとまず金融機関側の怒りと反発を和らげたい意向とされる。だが、金融筋の一人は「破綻の真相究明と責任の所在の明確化が先」と声を荒らげる。今後の展開次第では日本郵船の経営体制を揺さぶる事態ともなりかねない。
運賃市況下落の波が追い打ち
そんな日本郵船の足元へひたひたと押し寄せているのが、ここにきて再びピッチを早めつつある運賃市況下落の波だ。昨年八月には一時一千六十六にまで回復していたバルチック海運指数(一九八五年=一千)は同十二月には五百十九に悪化。足元は四百を大きく割り込み、史上最低の水準にまで落ち込んでいる。中国をはじめとした新興国の景気減速を受けて鉄鉱石や石炭などの資源需要が低迷、それらを運ぶバラ積み船の需給バランス悪化に歯止めがかからないためだ。
日本郵船が一月二十九日に発表した一五年度第3四半期決算(十~十二月)では経常利益が前年同期の二百四十八億円から約四割も減少。営業利益七百五十億円、経常利益八百億円などとしていた通期の利益計画の下方修正にも追い込まれた。
日本郵船では一円円安が進むごとに経常利益が年約十一億円押し上げられ、船舶重油など燃料価格が一トン当たり十ドル下がれば、同様に約十三億円がかさ上げされるとされている。上期は運賃市況低迷による減益要因をこうした円安・燃料安効果でカバーして三八%強の経常増益を確保したが、下期は運賃市況の下落幅が余りに大きく、年明け以降の大幅な原油安効果も食い潰される格好だ。
海運業界関係者によると、一四年まで二年連続で減少したバラ積み船の竣工隻数は一五年には増加に転じ、一六年以降もしばらくは新造船による供給圧力が続くという。日用品などを運ぶコンテナ船も新船建造に歯止めがかかる気配はない。なかでも攻勢をかけているのが、同船舶で世界シェア一五%と圧倒的な首位に立つデンマークのAPモラー・マースクグループ傘下のマースクライン。一四年末には積載能力を日本郵船支配下の船舶より約八割も高めた超大型コンテナ船を日本に就航、今後も相次ぎ投入していく方針だとされている。
「そんなことになれば運賃市況は間違いなく底割れする」。日本郵船関係者の一人は青ざめる。
無論、日本郵船とて市況変動の波にただただ翻弄されているだけではない。一四年度からの中期計画では①短期的変動に左右されにくい中長期運搬契約の拡大②不採算船や老朽船の返船・売船はじめ船舶資産のスリム化―などを進める一方、海洋開発などのエネルギー関連分野やLNG輸送船に重点投資、新たな収益の柱として育成していく方針も打ち出した。ただ当面は日本郵船に恩恵をもたらす原油安は、海洋開発など新分野の将来性に暗く大きな影を落とす。
UOG破綻に伴う後始末の方向性が見通せないのと同様、日本郵船の行く手もまた、不透明だ。
©選択出版
〝事件〟は昨年十一月十一日、ある船主会社グループの経営破綻劇で幕を開けた。統括会社で船舶関連の契約業務請負や管理業務を行っているラムスコーポレーション(東京・港区)と実際に船舶を所有している三十八社のSPC(特別目的会社)から成るユナイテッドオーシャン・グループ(UOG)―その借入金の一部に債務不履行(デフォルト)が発生し、債権者の一人だったみずほフィナンシャルグループ系のリース準大手、興銀リースから会社更生法の適用申請を申し立てられたのだ。
UOGとラムス社は新船建造費の融資を受けるに際し、金融機関との間でクロスデフォルト条項を交わしていたとされている。借入金が一つでもデフォルトを起こせば、残りの借入金が返済期限を迎えていなくても、すべてがデフォルトを起こしたとみなされ、債権者が返済を要求できる仕組み。興銀リースはその発動に踏み切ったのだ。
そして同十二月三十一日、UOGは東京地裁から会社更生法手続き開始の決定を受ける。興銀リース自体の焦げ付きは三十七億円弱に過ぎなかったものの、グループ全体での負債総額は約一千四百億円にも上った。規模としては昨年で最大級の企業倒産だった。
とはいえ、ここまでなら規模こそ大きいものの、それこそ「どこにでもある破綻劇」(金融筋)。すでに更生法の手続き開始が決まった以上、その枠組みに沿って清々粛々と法的整理を進めていけば済む。
ところが―事はこれでは終わらなかったのである。倒産と相前後する形で、UOGが偽りの契約内容をもとに金融機関から不正に融資を引き出していた疑いが浮上したうえ、日本郵船がどうやらそれに一枚嚙んでいるのでは、といった疑惑までが銀行関係者らの間でまことしやかに取り沙汰されはじめたからだ。
「クルマも女もあてがった」
実はUOGは「極めて特殊な船主会社」(海運業界筋)だとされている。シンガポールに二十四社、パナマに十四社登記されているSPCを通じて、七万トン以上のパナマックス船十三隻、四万トン以上のハンディマックス船九隻、自動車船七隻など三十八隻を保有しているが、そのすべてを日本郵船一社だけに貸し付けているためだ。
通常三十八隻もの船を所有していれば、複数の海運会社に船を貸して、リスク分散を図るのが真っ当な経営の在り方だ。海運会社が破綻すれば傭船料を取りっぱぐれる恐れもあるからだ。実際、昨年九月末には売上高で業界五位の第一中央汽船が民事再生法の適用を申請するなど、直近での破綻劇も起こっている。
一方で、船主からすれば日本郵船のような相対的に財務体質の良好な海運会社とできるだけ多くの取引関係を持ちたいと思うのも本音だろう。それだけに同社をめぐる船主間の貸し付け競争は激しい。とりわけ二〇一二年以降は、海運市況や船価が底に達したとみたファンドなど世界の投機マネーが大量に造船市場に流入、競争はさらにエスカレートしている。それなのに「なぜUOGがここまで日本郵船に食い込めたのか」。海運大手三社の一角、商船三井幹部の一人もしきりと首を捻る。
UOGはインド人のヴィパン・クマール・シャルマ社長が一代で起こした会社だ。十歳のときから日本で育った人物で、一九九一年に設立した。日本郵船との間に無論、何の資本関係もない。それが日本郵船の全傭船隻数五百十四隻(一五年九月末)の七・四%を占めるまでに取引を拡大させたのだ。
業界関係者によると、シャルマ社長による日本郵船首脳や幹部らに対する〝接待攻勢〟は「実はそのスジでは有名な話だった」という。一説では経営陣や役員候補の人材に対し、社長自身が「相当なカネを使った。クルマも女もあてがった」などと吹聴していたとか。なかでも経団連副会長をつとめ、「最高実力者」(日本郵船関係者)とされた草刈隆郎元社長・会長(現特別顧問)とは「因縁浅からぬものがあった」(周辺筋)とされている。
だが、それならばどうしてUOGは破綻しなければならなかったのか。船主会社は取引相手の海運会社が存続している限り、安定・継続的に傭船料が入ってくるストックビジネスだ。本業に専念してさえいれば「大儲けはできないにしても、借入金の返済に行き詰まるほど資金繰りに窮するようなことはほとんどない」(メガバンク筋)ともいわれている。まして傭船先は大手三社のなかでも信用格付け最高位の日本郵船だ。
一般的に船主が新船を建造しようとする場合、その資金は総工費の一割を自己資金、残り九割を金融機関からの借り入れで賄うといわれている。しかし、金融機関側からすれば建造する船の傭船先が決まっており、その傭船契約の内容が確かなものでなければ危なっかしくて多額の融資など実行できるハズもない。
そこで金融機関側は融資に際して、建造される船がどこに貸し出されて、どれくらいの傭船料が見込めるのかを確認することになる。そのうえで傭船契約から得られる傭船料が元利金の返済原資となるようスキームを設計し、ファイナンスを実施するわけだ。「傭船料債権譲渡担保」と呼ばれる仕組みで、逆に船主側からすれば、傭船先から得られる傭船料の中から金融機関に対して決められた契約の通りに借入金の返済を行っていけば自ずと完済にまでこぎつけられることになる。デフォルトを起こすリスクは極めて少ない。なのに―UOGは破綻した。
初歩的ともいえる〝融資詐欺〟
こうして浮かび上がってきたのが、前述の疑惑だ。要するにUOGが起こすハズのないデフォルトを起こしたのは「そもそもUOGが金融機関に提出した傭船契約書そのものに何らかの瑕疵があったか、意図的に細工が施されたシロモノだったのではないか」(銀行筋)というわけだ。
そんななか業界関係者らの間で駆け巡っているのが、UOGと日本郵船との間の傭船料の取り決めは「異例ともいえる内容だった」との情報だ。当初の傭船料は固定だが、数年後には変動制に移行し、「国際的な海運市況に連動させる形になっていた」というのである。
事実とすれば業界の商慣行や常識から言って「あり得ない契約」(川崎汽船関係者)だろう。運賃相場の高止まりや上昇が続くのなら、確かに船主にとって変動制は好都合だ。しかし、ひとたび下落に転じれば傭船料収入が急減、金融機関への返済が滞り、あっという間に破綻に追い込まれるのは「火を見るより明らか」(メガバンク幹部)だからだ。
第一、こうした契約内容では回収不能リスクが高過ぎて、金融機関も融資自体を行わないし、行えない。強行して損失が生じれば「背任容疑で刑事責任すら問われかねない」(同前)ためだ。しかし現実には、UOGへの融資は実行された。だとすれば考えられるのは、UOGが市況連動型傭船料という事実をひた隠しにしていたか、契約書を完全固定制に偽造していたかということくらいしかあるまい。
金融関係者によるとシップファイナンスの場合、借り入れを希望する船主が提出する契約書類は必ずしも原本である必要はなく、コピーで十分なのだという。そこでこれを悪用する形で紛い物を作成、本物に見せかけて銀行側に提出していたのではないか――。大手銀行のある幹部はこう推察する。
典型的で初歩的ともいえる“融資詐欺”だが、金融機関側からすれば提出された書類の真贋はともあれ、契約書に記載され、傭船料収入ひいては借入金返済原資の裏付けともなっている「日本郵船」の肩書と信用力は絶対的にモノを言う。「資金需要の伸び悩みに困っていただけに、一も二もなく融資に応じたのでは……」。大手地銀幹部は思いを巡らせる。
何かしらの作為とある種の不実
それにしても日本郵船は「非常識」とされている傭船料市況スライドの契約をなぜUOGに押し付けたのだろう。船主会社と海運会社の力関係を利用した、いわば優越的地位の乱用といえなくもないが、こうした契約内容ではUOGが金融機関から新船建造のための融資を引き出せないであろうことは「日本郵船側も当然、認識していたハズだ」(海運業界関係者)。
だとすれば、それでもなお融資を引き出そうとするとUOGが、何らかの不正に手を染めざるを得なくなる可能性も「当然ながら予見できたハズ」(業界筋)。にもかかわらず、日本郵船は目をつぶっていたばかりか、実際に融資が引き出されて三十八隻もの船が建造されるに至るまでひたすら沈黙を続けた。「そこに何かしらの作為とある種の不実を感じざるを得ない」。金融関係者の一人は呟く。騙された―の声が燻る所以か。
UOGが興銀リース以外のどんな金融機関とどれくらいの規模の取引があったのか、現時点ではすべてが具体的に明確になっているわけではない。しかし各大手銀行ともここ数年揃ってシップファイナンスに力を入れてきた経緯もあるだけに、その大半が今回の破綻に巻き込まれたのはほぼ確実。事情通らの間では「みずほ銀行や商工中金、さらには日本郵船本体のメーンバンクでもある三菱東京UFJ銀行なども焦げ付きを抱えたらしい」といった観測が飛び交う。また、りそなホールディングスが二〇一五年度上期(四~九月)決算で大幅な減益に転じる原因となった約三百二十二億円の個別貸倒引当金の計上も「その大部分がUOG向けだった」(市場関係者)とも取り沙汰されている。
日本郵船ではUOGの破綻後も同社との傭船契約を解除せず、現行契約の残存期間中はそのまま船を借りて傭船料を支払い続けていくことで、ひとまず金融機関側の怒りと反発を和らげたい意向とされる。だが、金融筋の一人は「破綻の真相究明と責任の所在の明確化が先」と声を荒らげる。今後の展開次第では日本郵船の経営体制を揺さぶる事態ともなりかねない。
運賃市況下落の波が追い打ち
そんな日本郵船の足元へひたひたと押し寄せているのが、ここにきて再びピッチを早めつつある運賃市況下落の波だ。昨年八月には一時一千六十六にまで回復していたバルチック海運指数(一九八五年=一千)は同十二月には五百十九に悪化。足元は四百を大きく割り込み、史上最低の水準にまで落ち込んでいる。中国をはじめとした新興国の景気減速を受けて鉄鉱石や石炭などの資源需要が低迷、それらを運ぶバラ積み船の需給バランス悪化に歯止めがかからないためだ。
日本郵船が一月二十九日に発表した一五年度第3四半期決算(十~十二月)では経常利益が前年同期の二百四十八億円から約四割も減少。営業利益七百五十億円、経常利益八百億円などとしていた通期の利益計画の下方修正にも追い込まれた。
日本郵船では一円円安が進むごとに経常利益が年約十一億円押し上げられ、船舶重油など燃料価格が一トン当たり十ドル下がれば、同様に約十三億円がかさ上げされるとされている。上期は運賃市況低迷による減益要因をこうした円安・燃料安効果でカバーして三八%強の経常増益を確保したが、下期は運賃市況の下落幅が余りに大きく、年明け以降の大幅な原油安効果も食い潰される格好だ。
海運業界関係者によると、一四年まで二年連続で減少したバラ積み船の竣工隻数は一五年には増加に転じ、一六年以降もしばらくは新造船による供給圧力が続くという。日用品などを運ぶコンテナ船も新船建造に歯止めがかかる気配はない。なかでも攻勢をかけているのが、同船舶で世界シェア一五%と圧倒的な首位に立つデンマークのAPモラー・マースクグループ傘下のマースクライン。一四年末には積載能力を日本郵船支配下の船舶より約八割も高めた超大型コンテナ船を日本に就航、今後も相次ぎ投入していく方針だとされている。
「そんなことになれば運賃市況は間違いなく底割れする」。日本郵船関係者の一人は青ざめる。
無論、日本郵船とて市況変動の波にただただ翻弄されているだけではない。一四年度からの中期計画では①短期的変動に左右されにくい中長期運搬契約の拡大②不採算船や老朽船の返船・売船はじめ船舶資産のスリム化―などを進める一方、海洋開発などのエネルギー関連分野やLNG輸送船に重点投資、新たな収益の柱として育成していく方針も打ち出した。ただ当面は日本郵船に恩恵をもたらす原油安は、海洋開発など新分野の将来性に暗く大きな影を落とす。
UOG破綻に伴う後始末の方向性が見通せないのと同様、日本郵船の行く手もまた、不透明だ。
©選択出版
掲載物の無断転載・複製を禁じます©選択出版