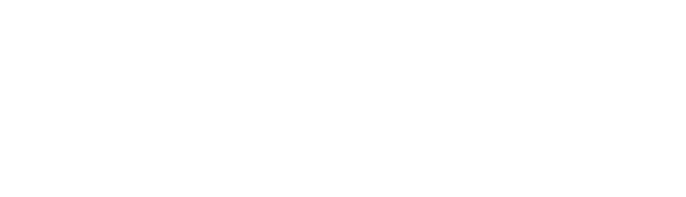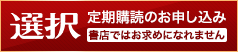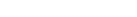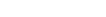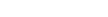「入院難民」が溢れる都市部
医療弱者「見殺し政策」が進行中
2020年1月号公開
「厚生労働省に任せていたら、都民はまともな医療が受けられなくなる」。都内のクリニックに勤務する内科医は断言する。医療の高度化・専門化が進む都心部では、肺炎や胃腸炎、喘息発作など数日間の入院治療が必要になる「普通の病気」に対処できる中小病院が淘汰の波にさらされている。厚労省が病床数や医師数を統制する中、統制は利権を生み、利権は利益を尺度に患者を選別する。しわ寄せを受けるのは、高齢者と中小病院という医療弱者だ。治療を受けられずに漂流する「入院難民」が都市部から全国に広がりつつある。
ある八十代の男性のケースを紹介しよう。男性は心臓の持病があり、複数の薬を飲んでいた。三年前に胃がんの手術を経験し、前立腺がんのホルモン治療も受けている。心臓とがんは専門病院、血圧も高く近所のクリニックに通院している。胃がんの手術をきっかけに郊外の持ち家を売って、夫婦で港区に引っ越してきた。
男性は昨年八月、三十九度の熱を出した。倦怠感がひどいため、かかりつけ医を受診したところ、風邪と診断された。薬を処方されたが改善しなかった。食事も摂れず、歩行時にはふらつくようになった。かかりつけ医に電話したところ、「肺炎の可能性もあり、このままだと心臓にも悪いから、入院が必要」と言われた。この医師は幾つかの病院に電話してくれたが、どこもベッドは空いていなかった。
心臓の専門病院の担当医からは、口調こそ丁寧だったが「心臓でなければ、うちでは診ません」と断られた。困り果てた患者が頼ったのが、知人の内科医だ。この内科医は江東区の病院長に電話して、男性を入院させてもらった。肺炎と診断され、抗生剤を点滴されると、ほどなく状態は改善し、二週間ほどで退院した。
東京・港区は「消滅都市」以下
都心には多くの病院がある。なぜ、こんな患者のたらい回しのようなことになるのだろうか。それは都心部には大学病院や専門病院は多いが、「肺炎などありふれた病気を診療する普通の病院が極端に少ない」(冒頭の内科医)からだ。
東京には多くの医師がいる。二〇一六年末時点で、人口十万人あたりの医師数は三百四人。全国平均の二百四十人を大きく上回り、徳島県・高知県に次いで全国三位だ。病床も多い。一八年九月時点で、十二万八千百八十九床で、全国一位だ。ところが、人口十万人あたりにすると九百二十七床となり、全国四十五位となる。東京より少ないのは、神奈川県(八百十一床)、埼玉県(八百五十七床)だけだ。東京で医師数と病床数が乖離するのは、大学病院が多いからだ。十三の医学部があり、分院を含む三十一の病院で一万五千九百二十五床の病床を有する。
問題は大学病院が扱うのが、がんや心臓病の治療などの高度医療にほぼ限定されることだ。普通の肺炎や胃腸炎の患者は「表向きは断らないことになっているが、あまり歓迎されない」(大学病院勤務医)。この状況は心臓病やがんの専門病院、さらに一流の総合病院も変わらない。
大学病院や専門病院を受診するのは容易ではない。受診するには開業医などの紹介状が必要だ。厚労省は、紹介状なしで受診した患者からは、五千円以上の追加料金を徴収することを義務付けている。この結果、都心部に大病院は沢山あるものの、胃腸炎などの「普通の病気」では容易に入院できなくなっている。
港区の場合、済生会中央、虎の門、国際医療福祉大学三田、東京慈恵会医科大学附属、山王、北里大学北里研究所、愛育、東京大学医科学研究所附属、心臓血管研究所付属、赤坂見附前田、古川橋、東京高輪、西原の計十三病院がある。済生会中央など十病院は大学病院、高度医療機関、専門病院、あるいは富裕層向け病院である。西原病院は療養型だから、急性疾患は受け付けない。普通の患者を受け入れるのは、古川橋病院と東京高輪病院だけだ。
両病院の病床数は合計して三百しかない。厚労省は紹介状なしで受診できる病院を、現在の四百床未満から二百床未満に制限する方針だから、紹介状なしで受診できる病院は古川橋病院だけになり、病床は人口十万人あたり二十・二床になる。これは「消滅都市」と呼ばれる地方都市以下だ。
文京区も状況は変わらない。文教区にある九つの病院のうち、東京大学医学部附属病院など六病院は大学病院あるいは専門病院。特殊疾患・介護療養型病院が一つある。つまり、一般病床や地域包括ケア病床を有する「普通」の病院は二病院だけで、病床数は合計百六十一床。人口十万人あたり七十三床だ。
高齢者の入院ベッド探しは至難
普通の病院が減っているのは東京だけではない。大阪でも「入院難民」が溢れている。大阪市在住の四十八歳男性のケースをご紹介しよう。
男性は一八年十月、胃の不調を訴えて、地元の診療所を受診した。内視鏡検査を受けたところ、胃がんが判明した。医師は、以前から付き合いがある病院を紹介したが、受け入れてもらえなかった。十二月から療養型病院に業態を変更していたからだ。収益が低い一般病院をやめて、リハビリを中心とした専門病院に転換していたのだ。
仕方なく、医師は大阪赤十字病院を紹介したが、男性は術後わずか一週間で退院となった。急性期患者を受け入れる病院が収益を上げるには、在院日数を短縮し、できるだけ多くの手術をこなさねばならない。男性は、食事が摂れないので、定期的な点滴が必要。このため、専用のポートが埋め込まれ、苦痛に喘ぎながら地元の診療所に戻ってきた。
それでも、この男性は手術を受けることができただけでも恵まれている。深刻なのは高齢者だ。手術などの高度医療ができないので、大学病院や専門病院は引き取りたがらない。儲からないからだ。
前述の医師のところに呼吸器疾患で通院していた八十四歳の女性のケースは悲惨だ。昨年八月、便秘気味になり、大腸内視鏡検査を受けた。大きな腫瘤があり、大腸を閉塞させていたことが便秘の原因だった。根治は無理でも、腸閉塞を予防する治療をすべきだが、呼吸機能を考えると手術は難しい。どこの病院も受け入れず、「外来で宙ぶらりんの状態」(前出の内科医)が続き、今も便秘に悩む。腸閉塞になるのは時間の問題だ。
現在、高齢患者が入院ベッドを見つけるのは至難の業だ。このような患者を入院させても儲からないので、どこも引き取りたがらないのだ。「普通の」病気でも、高齢者にとっては、命の危険がある。なぜ、こんなことになるのだろうか。それは日本の医療が厳格な統制下にあるからだ。医師数、病床数、さらに診療報酬を厚労省が決める。統制が利権を生むのは古今東西変わらない。
利権の中で最大のものは診療報酬だ。厚労省が設置する中央社会保険医療協議会(中医協)で全国一律に決められる。都市と地方の報酬が同じなのだから、抑制すれば都市部の医療機関から経営難になるのは自明の理。厚労省は地域差を考慮して「地域加算」を認定しているが、都心部(東京都二十三区)の場合、入院で一日十八点(一点は十円)がつくだけだ。これでは焼け石に水だ。
医療費の総枠が抑制されるのだから、中医協は「不幸の再配分の場」(元中医協委員)となる。もちろん、不幸は弱者に押しつけられる。それが中小病院なのだ。
厚労省の利権構造が諸悪の根源
中医協を仕切るのは、事務局を務める厚労省だ。薬価は薬系技官、医療機関が受け取る診療報酬は医系技官が仕切る。彼らに影響を与えるのは、与党族議員、日本医師会、さらに最近は大病院だ。与党の族議員と日本医師会の関係は改めて説明する必要もないだろう。
なぜ、大病院が政治力をつけてきたのだろうか。まずは、大病院の多くが国公立あるいは独立行政法人であり、大勢の天下りや現役出向を抱えていることだ。例えば、千葉県病院局長の矢島鉄也氏は健康局長を務めた元医系技官だ。国立病院機構や地域医療機能推進機構などは常勤理事の約半分が厚労省関係者だ。
近年の特徴は民間の大病院への天下りが増えたことだ。昨年十月には東日本を中心に九つの病院などを経営する医療法人健育会グループで、七月まで健康局長を務めた宇都宮啓氏が副理事長として天下った。彼は〇八年、一四年の診療報酬改定に携わっている。
私大医学部への天下りは枚挙に暇がない。松谷有希雄・国際医療福祉大学副学長、三浦公嗣・慶應義塾大学教授、佐藤敏信・久留米大学特命教授などは局長経験のある元医系技官だ。
診療報酬を仕切るのは後輩の医系技官たちだ。後輩から情報を得ると同時に、自らの要望も伝え、大病院の声は診療報酬改定に反映される。二〇年春の診療報酬改定で「救急病院における勤務医の働き方改革」に充てるため、特例として〇・〇八%の引き上げが決まったことなど、その典型だ。
経営難に喘ぐ中小病院は蚊帳の外だ。ここに「再就職」を希望する奇特な医系技官幹部はいない。彼らの声は届かないのだ。このため、肺炎や胃腸炎など、中小病院が扱う医療行為の診療報酬は安いままで据え置かれる。「肺炎で一週間程度、入院治療しても、総収入は十二万円程度」(病院事務長)。これでは都市部ではやっていけない。
都市部の中小病院が置かれた状況は時々刻々と悪化しつつある。医師の退職が止まらないのだ。ある病院幹部は「五人いた内科医は三人になってしまった」という。辞めた理由は、待遇が悪いからだ。収益が悪いから、医師の給与を上げることはできない。この病院では四十代半ばの常勤医の年収はおよそ一千万円。勤務医の平均年収一千六百九十六万円の六割程度だ。
生活費を稼ぐためには、アルバイトに行かねばならない。その場合、病院からは埋め合わせを求められる。週に一回午前か午後に行くと、終業時間を一時間遅らせねばならない。さらに月に三回の当直もこなす。経営者から利益を上げることを求められている病院長の口癖は「救急患者は断るな」。脳神経外科は常にオンコール体制だ。常勤医は三人しかいないため、週に二回は担当する。その日は、遠出はもちろん、酒も飲めない。報酬はわずか五千円だ。
この病院の人件費率は五六%だ。ここまで切り詰めても病院の経営は苦しい。一七年度の病院収益は前年より一〇%落ちた。医師の退職が相次いだからだ。医師が確保できなければ、経営は立ちゆかない。最終的には撤退するしかない。文京区を見てみよう。
医療法人社団大坪会は、文京区に二つしかない「普通の病院」である東都文京病院を経営する。一四年四月に日立製作所が運営する小平記念東京日立病院を継承した。実は、大坪会は、〇七年四月に文京区大塚の日通東京病院を買収し、小石川東京病院と名称変更したが、一七年四月に診療を休止した。東都文京病院が二の舞いにならない保証はない。そうなれば文京区の医療は崩壊する。
都市部の医療崩壊は止まらない
都市部の医療を守るには、過剰になった大学病院などの病床数と診療報酬を下げ、中小病院に振り向けるべきだが、厚労省は、「状況は熟知しており、現状を黙認している」(厚労官僚)だけだ。
「開業医や大病院の利権に切り込めば、族議員やOBたちからクレームが入るし、自らの天下り先を減らすだけ」(同前)だが、中小病院の診療報酬を下げても、誰からもクレームはこない。これをいいことに「中小病院は社会的入院が多い」などと批判して、その診療報酬を下げ続けてきた。こうして都市部の中小病院は壊滅してしまった。今や、病気になっても、入院できるところはなくなってしまった。都市部の医療崩壊は厚労省の責任だ。
ところが、厚労省に反省の素振りはない。本質は都市部の中小病院を崩壊に導くものであるにもかかわらず、「在宅医療推進」や「医療・介護連携」などのスローガンを掲げ、国民の目を問題からそらしている。
少子高齢化が進むわが国で医療費抑制は喫緊の課題だ。厚労省は昨年九月、「再編・統合について特に議論が必要」な病院として四百二十四の病院の実名を公開。二〇年度予算案には、病床の削減を推し進めるために約八十四億円を盛り込んでいる。過剰な病床により不要な治療が蔓延しているとの声も一理ある。しかし、厚労省が「錦の御旗」のごとく掲げる「国民皆保険制度」の本質は、誰もが平等に医療サービスを受けられることだ。日本の医療崩壊は止まりそうにない。
ある八十代の男性のケースを紹介しよう。男性は心臓の持病があり、複数の薬を飲んでいた。三年前に胃がんの手術を経験し、前立腺がんのホルモン治療も受けている。心臓とがんは専門病院、血圧も高く近所のクリニックに通院している。胃がんの手術をきっかけに郊外の持ち家を売って、夫婦で港区に引っ越してきた。
男性は昨年八月、三十九度の熱を出した。倦怠感がひどいため、かかりつけ医を受診したところ、風邪と診断された。薬を処方されたが改善しなかった。食事も摂れず、歩行時にはふらつくようになった。かかりつけ医に電話したところ、「肺炎の可能性もあり、このままだと心臓にも悪いから、入院が必要」と言われた。この医師は幾つかの病院に電話してくれたが、どこもベッドは空いていなかった。
心臓の専門病院の担当医からは、口調こそ丁寧だったが「心臓でなければ、うちでは診ません」と断られた。困り果てた患者が頼ったのが、知人の内科医だ。この内科医は江東区の病院長に電話して、男性を入院させてもらった。肺炎と診断され、抗生剤を点滴されると、ほどなく状態は改善し、二週間ほどで退院した。
東京・港区は「消滅都市」以下
都心には多くの病院がある。なぜ、こんな患者のたらい回しのようなことになるのだろうか。それは都心部には大学病院や専門病院は多いが、「肺炎などありふれた病気を診療する普通の病院が極端に少ない」(冒頭の内科医)からだ。
東京には多くの医師がいる。二〇一六年末時点で、人口十万人あたりの医師数は三百四人。全国平均の二百四十人を大きく上回り、徳島県・高知県に次いで全国三位だ。病床も多い。一八年九月時点で、十二万八千百八十九床で、全国一位だ。ところが、人口十万人あたりにすると九百二十七床となり、全国四十五位となる。東京より少ないのは、神奈川県(八百十一床)、埼玉県(八百五十七床)だけだ。東京で医師数と病床数が乖離するのは、大学病院が多いからだ。十三の医学部があり、分院を含む三十一の病院で一万五千九百二十五床の病床を有する。
問題は大学病院が扱うのが、がんや心臓病の治療などの高度医療にほぼ限定されることだ。普通の肺炎や胃腸炎の患者は「表向きは断らないことになっているが、あまり歓迎されない」(大学病院勤務医)。この状況は心臓病やがんの専門病院、さらに一流の総合病院も変わらない。
大学病院や専門病院を受診するのは容易ではない。受診するには開業医などの紹介状が必要だ。厚労省は、紹介状なしで受診した患者からは、五千円以上の追加料金を徴収することを義務付けている。この結果、都心部に大病院は沢山あるものの、胃腸炎などの「普通の病気」では容易に入院できなくなっている。
港区の場合、済生会中央、虎の門、国際医療福祉大学三田、東京慈恵会医科大学附属、山王、北里大学北里研究所、愛育、東京大学医科学研究所附属、心臓血管研究所付属、赤坂見附前田、古川橋、東京高輪、西原の計十三病院がある。済生会中央など十病院は大学病院、高度医療機関、専門病院、あるいは富裕層向け病院である。西原病院は療養型だから、急性疾患は受け付けない。普通の患者を受け入れるのは、古川橋病院と東京高輪病院だけだ。
両病院の病床数は合計して三百しかない。厚労省は紹介状なしで受診できる病院を、現在の四百床未満から二百床未満に制限する方針だから、紹介状なしで受診できる病院は古川橋病院だけになり、病床は人口十万人あたり二十・二床になる。これは「消滅都市」と呼ばれる地方都市以下だ。
文京区も状況は変わらない。文教区にある九つの病院のうち、東京大学医学部附属病院など六病院は大学病院あるいは専門病院。特殊疾患・介護療養型病院が一つある。つまり、一般病床や地域包括ケア病床を有する「普通」の病院は二病院だけで、病床数は合計百六十一床。人口十万人あたり七十三床だ。
高齢者の入院ベッド探しは至難
普通の病院が減っているのは東京だけではない。大阪でも「入院難民」が溢れている。大阪市在住の四十八歳男性のケースをご紹介しよう。
男性は一八年十月、胃の不調を訴えて、地元の診療所を受診した。内視鏡検査を受けたところ、胃がんが判明した。医師は、以前から付き合いがある病院を紹介したが、受け入れてもらえなかった。十二月から療養型病院に業態を変更していたからだ。収益が低い一般病院をやめて、リハビリを中心とした専門病院に転換していたのだ。
仕方なく、医師は大阪赤十字病院を紹介したが、男性は術後わずか一週間で退院となった。急性期患者を受け入れる病院が収益を上げるには、在院日数を短縮し、できるだけ多くの手術をこなさねばならない。男性は、食事が摂れないので、定期的な点滴が必要。このため、専用のポートが埋め込まれ、苦痛に喘ぎながら地元の診療所に戻ってきた。
それでも、この男性は手術を受けることができただけでも恵まれている。深刻なのは高齢者だ。手術などの高度医療ができないので、大学病院や専門病院は引き取りたがらない。儲からないからだ。
前述の医師のところに呼吸器疾患で通院していた八十四歳の女性のケースは悲惨だ。昨年八月、便秘気味になり、大腸内視鏡検査を受けた。大きな腫瘤があり、大腸を閉塞させていたことが便秘の原因だった。根治は無理でも、腸閉塞を予防する治療をすべきだが、呼吸機能を考えると手術は難しい。どこの病院も受け入れず、「外来で宙ぶらりんの状態」(前出の内科医)が続き、今も便秘に悩む。腸閉塞になるのは時間の問題だ。
現在、高齢患者が入院ベッドを見つけるのは至難の業だ。このような患者を入院させても儲からないので、どこも引き取りたがらないのだ。「普通の」病気でも、高齢者にとっては、命の危険がある。なぜ、こんなことになるのだろうか。それは日本の医療が厳格な統制下にあるからだ。医師数、病床数、さらに診療報酬を厚労省が決める。統制が利権を生むのは古今東西変わらない。
利権の中で最大のものは診療報酬だ。厚労省が設置する中央社会保険医療協議会(中医協)で全国一律に決められる。都市と地方の報酬が同じなのだから、抑制すれば都市部の医療機関から経営難になるのは自明の理。厚労省は地域差を考慮して「地域加算」を認定しているが、都心部(東京都二十三区)の場合、入院で一日十八点(一点は十円)がつくだけだ。これでは焼け石に水だ。
医療費の総枠が抑制されるのだから、中医協は「不幸の再配分の場」(元中医協委員)となる。もちろん、不幸は弱者に押しつけられる。それが中小病院なのだ。
厚労省の利権構造が諸悪の根源
中医協を仕切るのは、事務局を務める厚労省だ。薬価は薬系技官、医療機関が受け取る診療報酬は医系技官が仕切る。彼らに影響を与えるのは、与党族議員、日本医師会、さらに最近は大病院だ。与党の族議員と日本医師会の関係は改めて説明する必要もないだろう。
なぜ、大病院が政治力をつけてきたのだろうか。まずは、大病院の多くが国公立あるいは独立行政法人であり、大勢の天下りや現役出向を抱えていることだ。例えば、千葉県病院局長の矢島鉄也氏は健康局長を務めた元医系技官だ。国立病院機構や地域医療機能推進機構などは常勤理事の約半分が厚労省関係者だ。
近年の特徴は民間の大病院への天下りが増えたことだ。昨年十月には東日本を中心に九つの病院などを経営する医療法人健育会グループで、七月まで健康局長を務めた宇都宮啓氏が副理事長として天下った。彼は〇八年、一四年の診療報酬改定に携わっている。
私大医学部への天下りは枚挙に暇がない。松谷有希雄・国際医療福祉大学副学長、三浦公嗣・慶應義塾大学教授、佐藤敏信・久留米大学特命教授などは局長経験のある元医系技官だ。
診療報酬を仕切るのは後輩の医系技官たちだ。後輩から情報を得ると同時に、自らの要望も伝え、大病院の声は診療報酬改定に反映される。二〇年春の診療報酬改定で「救急病院における勤務医の働き方改革」に充てるため、特例として〇・〇八%の引き上げが決まったことなど、その典型だ。
経営難に喘ぐ中小病院は蚊帳の外だ。ここに「再就職」を希望する奇特な医系技官幹部はいない。彼らの声は届かないのだ。このため、肺炎や胃腸炎など、中小病院が扱う医療行為の診療報酬は安いままで据え置かれる。「肺炎で一週間程度、入院治療しても、総収入は十二万円程度」(病院事務長)。これでは都市部ではやっていけない。
都市部の中小病院が置かれた状況は時々刻々と悪化しつつある。医師の退職が止まらないのだ。ある病院幹部は「五人いた内科医は三人になってしまった」という。辞めた理由は、待遇が悪いからだ。収益が悪いから、医師の給与を上げることはできない。この病院では四十代半ばの常勤医の年収はおよそ一千万円。勤務医の平均年収一千六百九十六万円の六割程度だ。
生活費を稼ぐためには、アルバイトに行かねばならない。その場合、病院からは埋め合わせを求められる。週に一回午前か午後に行くと、終業時間を一時間遅らせねばならない。さらに月に三回の当直もこなす。経営者から利益を上げることを求められている病院長の口癖は「救急患者は断るな」。脳神経外科は常にオンコール体制だ。常勤医は三人しかいないため、週に二回は担当する。その日は、遠出はもちろん、酒も飲めない。報酬はわずか五千円だ。
この病院の人件費率は五六%だ。ここまで切り詰めても病院の経営は苦しい。一七年度の病院収益は前年より一〇%落ちた。医師の退職が相次いだからだ。医師が確保できなければ、経営は立ちゆかない。最終的には撤退するしかない。文京区を見てみよう。
医療法人社団大坪会は、文京区に二つしかない「普通の病院」である東都文京病院を経営する。一四年四月に日立製作所が運営する小平記念東京日立病院を継承した。実は、大坪会は、〇七年四月に文京区大塚の日通東京病院を買収し、小石川東京病院と名称変更したが、一七年四月に診療を休止した。東都文京病院が二の舞いにならない保証はない。そうなれば文京区の医療は崩壊する。
都市部の医療崩壊は止まらない
都市部の医療を守るには、過剰になった大学病院などの病床数と診療報酬を下げ、中小病院に振り向けるべきだが、厚労省は、「状況は熟知しており、現状を黙認している」(厚労官僚)だけだ。
「開業医や大病院の利権に切り込めば、族議員やOBたちからクレームが入るし、自らの天下り先を減らすだけ」(同前)だが、中小病院の診療報酬を下げても、誰からもクレームはこない。これをいいことに「中小病院は社会的入院が多い」などと批判して、その診療報酬を下げ続けてきた。こうして都市部の中小病院は壊滅してしまった。今や、病気になっても、入院できるところはなくなってしまった。都市部の医療崩壊は厚労省の責任だ。
ところが、厚労省に反省の素振りはない。本質は都市部の中小病院を崩壊に導くものであるにもかかわらず、「在宅医療推進」や「医療・介護連携」などのスローガンを掲げ、国民の目を問題からそらしている。
少子高齢化が進むわが国で医療費抑制は喫緊の課題だ。厚労省は昨年九月、「再編・統合について特に議論が必要」な病院として四百二十四の病院の実名を公開。二〇年度予算案には、病床の削減を推し進めるために約八十四億円を盛り込んでいる。過剰な病床により不要な治療が蔓延しているとの声も一理ある。しかし、厚労省が「錦の御旗」のごとく掲げる「国民皆保険制度」の本質は、誰もが平等に医療サービスを受けられることだ。日本の医療崩壊は止まりそうにない。
掲載物の無断転載・複製を禁じます©選択出版