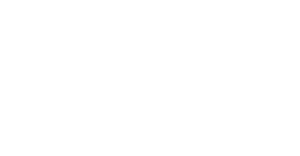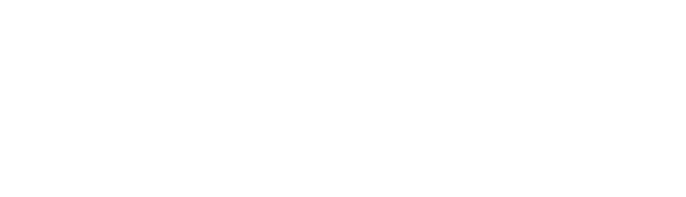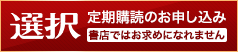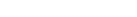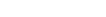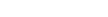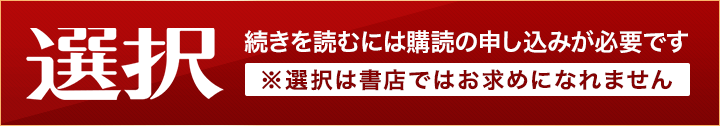超「老老介護」の壮絶(上)
母娘「共に認知症」の修羅場
2025年8月号
医学の進歩で寿命は延びても老化に伴う心身の機能低下は避けられず、かえって医療・介護の需要は増え、人口減などによる医師や介護職員の不足との落差が深刻になっている。「老老介護」で世話する側もされる側も一層高齢化し、どちらも認知症といった事例も珍しくなく、独居高齢者への対応も難しい。日本社会の未来の明暗を分ける後期高齢者との向き合い方を、2回にわたって考える。
「在宅医療」への過剰な期待
福井市で在宅医療を提供する「オレンジホームケアクリニック」の小坂真琴医師は今、超「老老介護」とでも呼ぶべき状況の広がりを痛感している。
東京大学医学部を卒業後、鹿児島県で初期研修を修了し、在宅医療を志して移住した福井市で日々の訪問診療とクリニックの症例の整理、分析を行う小坂氏はこれまで、在宅で44人の患者を診療した。うち21人が70歳代までの患者で、大部分はがんの終末期、心筋梗塞や脳卒中の後遺症、神経難病などを患っているものの、心身機能は維持され、パートナーと2人や独居での自立した生活も可能だ。
実際、・・・
「在宅医療」への過剰な期待
福井市で在宅医療を提供する「オレンジホームケアクリニック」の小坂真琴医師は今、超「老老介護」とでも呼ぶべき状況の広がりを痛感している。
東京大学医学部を卒業後、鹿児島県で初期研修を修了し、在宅医療を志して移住した福井市で日々の訪問診療とクリニックの症例の整理、分析を行う小坂氏はこれまで、在宅で44人の患者を診療した。うち21人が70歳代までの患者で、大部分はがんの終末期、心筋梗塞や脳卒中の後遺症、神経難病などを患っているものの、心身機能は維持され、パートナーと2人や独居での自立した生活も可能だ。
実際、・・・