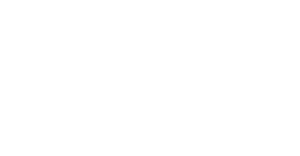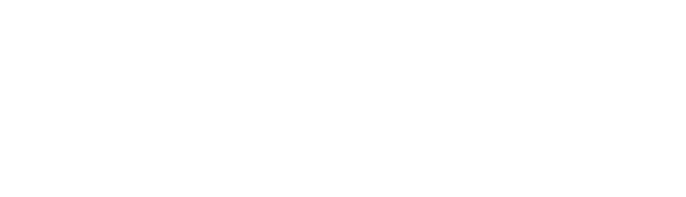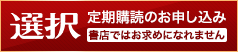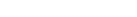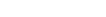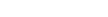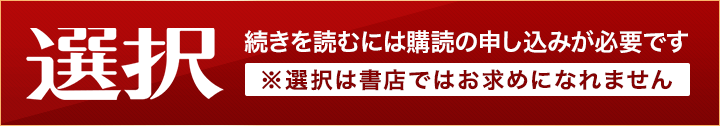群馬「みなかみ」にみる地方再生
水と森が「宝の山」になる時代
2025年8月号
連日の猛暑だが、日本の中央分水嶺を形成する群馬と新潟の県境の山岳地帯は、一年間で最も生命力にあふれ、生物の多様性を実感できる季節だ。ブナを中心とした広葉樹林が緑のドームのような空間をつくり、雪解け水が至る所で小さな滝となって流れ、昆虫や野鳥が混声する。連なる主峰の標高は2千m前後で、日本アルプスと比べると約1千mも低いが、樹林帯を抜けるとイワカガミ、シモツケソウなど高山植物が競い合うように咲き乱れる。この多様性を「ソフトパワー」と認識して「宝の山」に変えられるかどうかが、地方再生の鍵を握る。
谷川岳など群馬県北部の山岳地帯から流れてくる利根川は、「板東太郎」とも呼ばれ、関東平野を潤してきた。ただ、源流の探索は難航し、長く「謎」とされてきた。1894年の1回目の調査は、険しい岩場や滝などに阻まれ、戦前に突き止めることはできなかった。1954年の3回目の調査で、大水上山(1834m)の、夏でも残る雪渓が源流と判明する。湧き水ではなかったのだ。ぽとり、ぽとりと雪からとける一滴が集まり、細い川となり、赤谷川、渡良瀬川、鬼怒川などの支流を集めて日本一の流域面積を持つ大河となる。本流・・・
谷川岳など群馬県北部の山岳地帯から流れてくる利根川は、「板東太郎」とも呼ばれ、関東平野を潤してきた。ただ、源流の探索は難航し、長く「謎」とされてきた。1894年の1回目の調査は、険しい岩場や滝などに阻まれ、戦前に突き止めることはできなかった。1954年の3回目の調査で、大水上山(1834m)の、夏でも残る雪渓が源流と判明する。湧き水ではなかったのだ。ぽとり、ぽとりと雪からとける一滴が集まり、細い川となり、赤谷川、渡良瀬川、鬼怒川などの支流を集めて日本一の流域面積を持つ大河となる。本流・・・