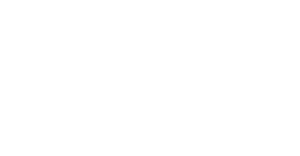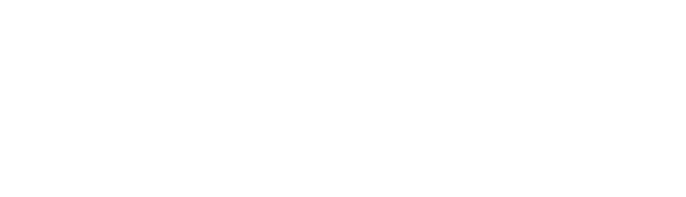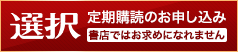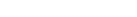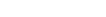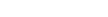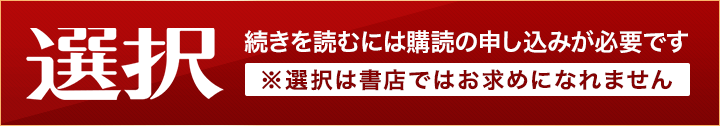超「老老介護」の壮絶(下)
「公助」を頼れぬ独居老人の実情
2025年9月号
医療、介護が必要な後期高齢者の数に見合った医師や看護職員が足りず、施設や病院で受け入れられないまま独り暮らしを余儀なくされる高齢者が増えていく―。〈超「老老介護」の壮絶〉の後編は、独居高齢者の実情を通じ、日本社会が直面する課題を見ていく。
「地域の老老介護」の課題
高齢化社会の進行とともに深刻度を増しているのが、孤独死の問題だ。警察庁の統計では2024年中に自宅で孤独死した人は7万6020人、その7割以上が70歳以上の高齢者だった。
老親の面倒を子がみれば孤独死が起きずに済んだ時代は遠く、23年の日本の「死亡年齢最頻値」は男性が88歳、女性は92歳。前編で取り上げた90歳代の母を70歳代の娘が介護した事例のように、老老介護には限界があり、高齢者施設の整備充実がなければ孤独死の増加は防げない。
厚生労働省の「令和5年(23年)介護サービス施設・事業所調査」によると、特別養護老人ホームの入所定員は64万人にとどまり、22万人が入所を待っている。国立社会保障・人口問題研究所の推計では、独・・・
「地域の老老介護」の課題
高齢化社会の進行とともに深刻度を増しているのが、孤独死の問題だ。警察庁の統計では2024年中に自宅で孤独死した人は7万6020人、その7割以上が70歳以上の高齢者だった。
老親の面倒を子がみれば孤独死が起きずに済んだ時代は遠く、23年の日本の「死亡年齢最頻値」は男性が88歳、女性は92歳。前編で取り上げた90歳代の母を70歳代の娘が介護した事例のように、老老介護には限界があり、高齢者施設の整備充実がなければ孤独死の増加は防げない。
厚生労働省の「令和5年(23年)介護サービス施設・事業所調査」によると、特別養護老人ホームの入所定員は64万人にとどまり、22万人が入所を待っている。国立社会保障・人口問題研究所の推計では、独・・・