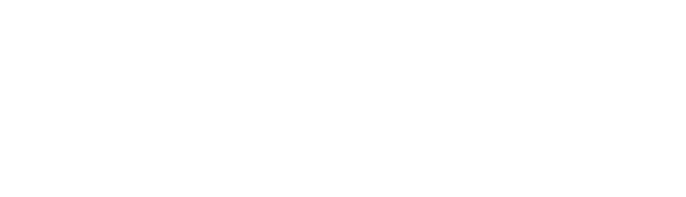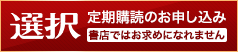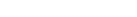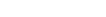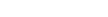「楽天」虚構の繁栄
三木谷「トリック」経営の限界
2015年1月号公開
「楽天の経営テーマは真にグローバルな会社です。社内の言語を日本語から英語に変えまして四年経ち、組織力が強くなってきています」
楽天の三木谷浩史社長は十一月五日、二〇一四年度第3四半期決算説明会で、英語でこう述べた。グローバル化を謳う同社は、一二年に電子書籍「コボ」(カナダ)、動画配信サイト「ウアキ」(スペイン)、一三年に動画翻訳ソーシャルサイト「ヴィキ」(シンガポール)、一四年に通信アプリ「ヴァイバー」(キプロス)、クーポンサイト「イーベイツ」(米国)と次々に海外企業を買収してみせた。「打倒アマゾン」を叫ぶが、これらを含めても流通総額の海外比率は一六%でしかない。
「楽天経済圏の世界展開」という誇大妄想に憑かれた三木谷氏は「虚構の繁栄」に酔いしれているが、世界どころか今や足元の国内事業すら成長モデル終焉の兆しが表れている。
海外で一つも成功例がない
「いやあ、海外M&A案件だらけですよ」。楽天の海外事業に携わる幹部はニヤニヤしながら言う。M&Aコンサルタントや投資銀行が足繁く出入りすることが恒常化しているという。だが、買収しても人材がなければコントロールできない。そこで英語が必要になる。「この業界は転職が多いが、そもそも英語を話す人は外資に行く。楽天に行きたがる人はまずいない」(外資系ネット大手関係者)という。つまり、純日本企業であり、六本木ヒルズの「色」に染められた同社は、「常識ある大人から当然のように避けられてきた」(同)ということだ。国内でのグローバル人材の確保に苦心してきた同社には、英語の公用語化くらいしか道がなかったのである。「四年でTOEICの点数が上がり、事業展開に活かせている」(三木谷氏)と自画自賛しているが、それは果たして本当なのか。楽天の海外事業を真剣に精査すれば、見えてくるのはポンコツぶりばかりだ。
同社は様々な国に進出し、買収、あるいは日本の楽天市場と同様のネットモールを立ち上げている。この実態を客観的に知るために、ネット上のトラフィック分析サイト「ALEXA」で計測をしてみよう。各国インターネット上での楽天の順位が分かる仕組みだ。まず日本の楽天市場「rakuten.co.jp」のトラフィック順位(十二月十六日計測)は、国内で七位、世界で八十一位だ。このデータはすべてのウェブサイトを含んでおり、例えば国内一位はヤフージャパン、二位はグーグルジャパン、三位はアマゾンジャパンとなる。
では「進出した各国での楽天市場」のトラフィック順位を見よう。例えば、インドネシアでは「raku
ten.co.id」という同国向けのサイトがあるが、順位は二百二十六位。まったくお話にならない状況だ。同様に、ドイツ(二百十五位)、スペイン(二百五十六位)、英国(六百五十二位)、オーストリア(二百六十三位)、米国(三百六十一位)、ブラジル(六百九位)と、散々な結果が連なる。
一方、アマゾンはこれらのほとんどで十位以内に入る。競合はアマゾンだけではない。例えばマレーシアでは、楽天の遥か上には「Mudah.my」(十二位)、「Lazada.com.my」(十六位)が並ぶ。十六位のラザダは、楽天と同時期に進出したドイツ系ベンチャーの運営である。つまり「アマゾンが進出していない比較的規模の小さい国へ進出する」という戦略で先を越されているのだ。海外事業スピードがいかに遅いかわかるだろう。
最大の成長市場である中国での事業では、バイドゥとの合弁「楽酷天」が失敗しており、インド市場でも同社は展開できていない。つまり成功している楽天市場は、海外に一つも存在しておらず、追い付くための戦略も将来性も見えてこない。だが、「グローバルな楽天」を演出したい三木谷氏としては、「流通総額」と称する取扱高の海外比率を多くしたいわけだ。そこで一計を案じた。
「この買収によってEコマース(EC)流通総額に占める海外比率は六%から一六%になります」(三木谷氏)
楽天は一四年九月、米ネット小売り関連サイトのイーベイツを十億ドルで買収した。イーベイツはウォルマートやヒューレット・パッカード等の提携先の小売りやメーカー直販のクーポンを配信し、ユーザーはクーポンをクリックしてから小売企業のサイトに行き、そこで商品購入すると、五%や一〇%のキャッシュバックになるというものだ。システム化した広告アフィリエイトサイトだが、そもそも楽天が〇五年に買収した米アフィリエイト広告大手リンクシェアの最大のパブリッシャー(媒体)がイーベイツである。
この買収でわかるのは「楽天市場型のモール事業では世界で勝ち目がない」と同社が認識しているということだ。明らかに「流通総額の嵩上げ」である。イーベイツは、日本でいえばインターネット送客事業を行う「カカクコム」と存在が似ているが、送客した契約先の売上高を「流通総額」と呼ぶのはトリッキーだ。例えるなら、スーパーのチラシを印刷している印刷所が、そのスーパーの売上高を「自社の取扱高」と発表しているようなものである。
イーベイツのEBITDAは二千五百十万ドル、純利益はわずか七百八十万ドル。つまり株価収益率百三十倍もの高額で買収したことになる。このEC流通総額の偽装によって、海外比率は今後上昇が見込めることになる。形ばかりの「グローバル化成功」が実現するというわけだ。
「打倒アマゾン」は冗談の世界
「打倒アマゾン」(三木谷氏)を口にする楽天の売り上げはアマゾンのたった十五分の一である。そのアマゾンは、高水準の先行投資を継続しており、利益率は低い。直近四年間の営業利益率推移で見ても、四%、二%、一%、一%と非常に低いが、粗利率は二二%、二二%、二五%、二七%と拡大しており、「仕入れ先へのバイイングパワー増大」「PB商品開発」「電子コンテンツ投入」等による粗利拡大が見てとれる。
そして、同社の財務戦略最大の特徴はキャッシュフロー(CF)経営である。同社は高い水準の減価償却費を計上しており、直近四年は五・七億ドル、十・八億ドル、二十一・六億ドル、三十二・五億ドルと急増している。利益水準と際どいバランスで設備投資を繰り返しており、これがまた営業CFを獲得する強みとなっている。一方、楽天では営業CFが時々マイナスになり、逆に投資CFがプラスになるなど「本業で稼げないキャッシュフロー構造」となっていることがわかる。
「楽天は世界的イノベーション企業として評価されています!」
楽天はフォーブス誌の世界のイノベーション企業ランクで十四位に入り、決算発表会でも三木谷氏は御満悦だった。だが、同誌We
b版の「気を付けろアマゾン、楽天とかいうのが参入してくるぞ」と題するコラムでは、痛烈な皮肉が書かれている。「楽天とイーベイツの組み合わせは、ECに革命を起こすだろう」という三木谷氏の言葉に対して「革命をもたらす? まさか。(中略)EC業界に必要なのはイノベーションではない。継続的なグローバリゼーションだ」「アマゾンは楽天の市場参入に特段恐れるべきだろうか。ハハハ、ノー」。これが、楽天に対する「世界の本音」である。
本業の限界を埋める金融部門
だが、海外事業以上に深刻なのは、国内の「楽天市場」にも暗雲が垂れ込めていることだ。
「(ソフトバンクの)孫さんのような(強気の)経営はできない。僕はどちらかと言うと堅実派だ」
三木谷氏はそう語っている。しかし、楽天の自己資本比率は一〇%を切っている。これはアグレッシブな財務戦略で知られるソフトバンクを下回る。楽天経済圏拡大のエンジンは、今やECではない。同社の事業は本業である「インターネットサービス」に加えて、「インターネット金融」「その他」と三事業があるが、事業別の営業利益(一三年度)は、インターネットサービスで四百七十五億円、インターネット金融は四百四十二億円と本業を凌駕しつつある。一四年一~九月で見ても、三百八十八億円と三百三十四億円である。
金融部門はカード、証券、銀行、生保、その他に分かれるが、なかでもカード(消費者金融)が大きい。楽天の成長エンジンは「誰でもつくれる」という評判の「楽天カード」である。EC事業での成長には限界が見え、同社では「ヨコテン(横展開)」と称してEC以外の事業で収益を確保しようとしている。
「サウンドハウスはこれまで三年間、楽天市場に商品を掲載しておりました。ところがこの度、楽天は一方的に弊社の決済口座としては楽天銀行の口座に一本化するということを決め、お客様に告知しました」
楽器販売のサウンドハウスは一四年十一月、リリースでこう発表した。「出店店舗の銀行口座を勝手に開設し、決済用口座としてはその口座しか認めないということは、これまでの日本の商習慣ではありえないことです」。これぞ楽天流。自社銀行の預金残高を増やすためなら、手段は選ばないのだ。
本業に関して言えば、楽天市場の出店数は一三年十二月をピークに減少を続けているという事実がある。これは初めてのことであり、明らかな転換点を迎えたと見ていい。成長モデルの終焉の兆しといえよう。「これからは数ではなく品質だ。相当数の出店申請を却下している」と三木谷氏は強調してみせる。「自分から断っている」と言いたいようだ。だが、楽天市場内で出店者同士の競争は激しく、高い出店料を払う店舗は既に疲弊し、店主たちは相次いで楽天を去っている。出店無料のヤフーショッピングが、楽天の後退に拍車をかける。さらには直販タイプの事業でも、同社は躓いた。
「楽天は、物流の素人ぶりを露呈してしまった」(業界筋)
日用品のスピード配送事業「楽天24」では、ヤフー傘下アスクルが運営するロハコやアマゾンに完敗し、バックエンドを支えるために一〇年三月に設立した楽天物流は、「設立半年で赤字に耐えきれずに撤退に追い込まれ、楽天が吸収合併することでもみ消した」(同前)のである。しまいには、この赤字の「楽天24」の事業を、一二年に買収した傘下のケンコーコムに押し付け、同社創業者である後藤玄利氏を退任に追い込んだ。
「偽装」は日常の風景
国内EC市場ですら、にわかに綻びが顕わになってきた。だがこれも、同社の社風を考えれば至極当然かもしれない。
「とてもいい商品で、びっくりしています。また利用したいと思います。」
これは、「めろん6969」という名前の楽天ユーザーが書いた様々な商品へのレビューである。八十件の商品に対して、この同じ文言でレビューが繰り返され、すべて一四年十二月十四日に投稿されている。こうした「サクラ」と思しき疑惑のレビューが、サイト内には恒常的に蔓延している。もはや「偽装」は、楽天市場の日常風景である。「閉店した店舗に、なぜか新しいレビューが次々と表示されていた」との証言を聞いても誰も驚かないだろう。楽天経済圏に蔓延る「疑惑」は枚挙にいとまがない。「電子書籍KOBOの強制無料プレゼント問題(端末普及率を水増し)」「KOBOの書籍出版点数水増し問題」「楽天スーパーセール二重価格表示問題」などは、周知の通りだ。あまり報道されなかったが、楽天銀行が「一週間円定期預金」で金利〇・五%という超高金利を六月二十三日に発表し、預金者を引き付けておいて同月二十九日に終了したという「高金利偽装疑惑」も発生した。消費者の目を眩ませる数々のトリックを弄する会社が、繁栄を続けることはない。
「ライブドアよりはだいぶマシだ」。六本木ヒルズ、森タワー十八階。十年ほど前に楽天本社を訪れた際の、筆者の率直な第一印象である。当時は堀江貴文氏の存在のおかげで、三木谷氏はまともな経営者であるかに見えた。それゆえ、同社の数々の無礼な振る舞いにも、日本社会は寛容に対応してきたのだ。
品川にある現在の楽天本社内には、「おもてなし」と書かれた同社のポスター、さらには三木谷氏の座右の銘「人は財なり」の書が飾ってある。「心にもないことを平気で言えるタイプ」(同社OB)ではないか。
カナダの電子書籍コボを買収して「電子書籍販売の課税逃れ」をする傍ら、政府の諮問機関「産業競争力会議」では、日本の未来について語っている。ただ、いくら綺麗事を並べても、本質はいつかは露見する。斜めに腰かけ、不敵な笑みを浮かべながら「おもてなしとは何か」を語る三木谷氏の姿が、虚飾に満ちた楽天の経営を如実に物語っている。
楽天の三木谷浩史社長は十一月五日、二〇一四年度第3四半期決算説明会で、英語でこう述べた。グローバル化を謳う同社は、一二年に電子書籍「コボ」(カナダ)、動画配信サイト「ウアキ」(スペイン)、一三年に動画翻訳ソーシャルサイト「ヴィキ」(シンガポール)、一四年に通信アプリ「ヴァイバー」(キプロス)、クーポンサイト「イーベイツ」(米国)と次々に海外企業を買収してみせた。「打倒アマゾン」を叫ぶが、これらを含めても流通総額の海外比率は一六%でしかない。
「楽天経済圏の世界展開」という誇大妄想に憑かれた三木谷氏は「虚構の繁栄」に酔いしれているが、世界どころか今や足元の国内事業すら成長モデル終焉の兆しが表れている。
海外で一つも成功例がない
「いやあ、海外M&A案件だらけですよ」。楽天の海外事業に携わる幹部はニヤニヤしながら言う。M&Aコンサルタントや投資銀行が足繁く出入りすることが恒常化しているという。だが、買収しても人材がなければコントロールできない。そこで英語が必要になる。「この業界は転職が多いが、そもそも英語を話す人は外資に行く。楽天に行きたがる人はまずいない」(外資系ネット大手関係者)という。つまり、純日本企業であり、六本木ヒルズの「色」に染められた同社は、「常識ある大人から当然のように避けられてきた」(同)ということだ。国内でのグローバル人材の確保に苦心してきた同社には、英語の公用語化くらいしか道がなかったのである。「四年でTOEICの点数が上がり、事業展開に活かせている」(三木谷氏)と自画自賛しているが、それは果たして本当なのか。楽天の海外事業を真剣に精査すれば、見えてくるのはポンコツぶりばかりだ。
同社は様々な国に進出し、買収、あるいは日本の楽天市場と同様のネットモールを立ち上げている。この実態を客観的に知るために、ネット上のトラフィック分析サイト「ALEXA」で計測をしてみよう。各国インターネット上での楽天の順位が分かる仕組みだ。まず日本の楽天市場「rakuten.co.jp」のトラフィック順位(十二月十六日計測)は、国内で七位、世界で八十一位だ。このデータはすべてのウェブサイトを含んでおり、例えば国内一位はヤフージャパン、二位はグーグルジャパン、三位はアマゾンジャパンとなる。
では「進出した各国での楽天市場」のトラフィック順位を見よう。例えば、インドネシアでは「raku
ten.co.id」という同国向けのサイトがあるが、順位は二百二十六位。まったくお話にならない状況だ。同様に、ドイツ(二百十五位)、スペイン(二百五十六位)、英国(六百五十二位)、オーストリア(二百六十三位)、米国(三百六十一位)、ブラジル(六百九位)と、散々な結果が連なる。
一方、アマゾンはこれらのほとんどで十位以内に入る。競合はアマゾンだけではない。例えばマレーシアでは、楽天の遥か上には「Mudah.my」(十二位)、「Lazada.com.my」(十六位)が並ぶ。十六位のラザダは、楽天と同時期に進出したドイツ系ベンチャーの運営である。つまり「アマゾンが進出していない比較的規模の小さい国へ進出する」という戦略で先を越されているのだ。海外事業スピードがいかに遅いかわかるだろう。
最大の成長市場である中国での事業では、バイドゥとの合弁「楽酷天」が失敗しており、インド市場でも同社は展開できていない。つまり成功している楽天市場は、海外に一つも存在しておらず、追い付くための戦略も将来性も見えてこない。だが、「グローバルな楽天」を演出したい三木谷氏としては、「流通総額」と称する取扱高の海外比率を多くしたいわけだ。そこで一計を案じた。
「この買収によってEコマース(EC)流通総額に占める海外比率は六%から一六%になります」(三木谷氏)
楽天は一四年九月、米ネット小売り関連サイトのイーベイツを十億ドルで買収した。イーベイツはウォルマートやヒューレット・パッカード等の提携先の小売りやメーカー直販のクーポンを配信し、ユーザーはクーポンをクリックしてから小売企業のサイトに行き、そこで商品購入すると、五%や一〇%のキャッシュバックになるというものだ。システム化した広告アフィリエイトサイトだが、そもそも楽天が〇五年に買収した米アフィリエイト広告大手リンクシェアの最大のパブリッシャー(媒体)がイーベイツである。
この買収でわかるのは「楽天市場型のモール事業では世界で勝ち目がない」と同社が認識しているということだ。明らかに「流通総額の嵩上げ」である。イーベイツは、日本でいえばインターネット送客事業を行う「カカクコム」と存在が似ているが、送客した契約先の売上高を「流通総額」と呼ぶのはトリッキーだ。例えるなら、スーパーのチラシを印刷している印刷所が、そのスーパーの売上高を「自社の取扱高」と発表しているようなものである。
イーベイツのEBITDAは二千五百十万ドル、純利益はわずか七百八十万ドル。つまり株価収益率百三十倍もの高額で買収したことになる。このEC流通総額の偽装によって、海外比率は今後上昇が見込めることになる。形ばかりの「グローバル化成功」が実現するというわけだ。
「打倒アマゾン」は冗談の世界
「打倒アマゾン」(三木谷氏)を口にする楽天の売り上げはアマゾンのたった十五分の一である。そのアマゾンは、高水準の先行投資を継続しており、利益率は低い。直近四年間の営業利益率推移で見ても、四%、二%、一%、一%と非常に低いが、粗利率は二二%、二二%、二五%、二七%と拡大しており、「仕入れ先へのバイイングパワー増大」「PB商品開発」「電子コンテンツ投入」等による粗利拡大が見てとれる。
そして、同社の財務戦略最大の特徴はキャッシュフロー(CF)経営である。同社は高い水準の減価償却費を計上しており、直近四年は五・七億ドル、十・八億ドル、二十一・六億ドル、三十二・五億ドルと急増している。利益水準と際どいバランスで設備投資を繰り返しており、これがまた営業CFを獲得する強みとなっている。一方、楽天では営業CFが時々マイナスになり、逆に投資CFがプラスになるなど「本業で稼げないキャッシュフロー構造」となっていることがわかる。
「楽天は世界的イノベーション企業として評価されています!」
楽天はフォーブス誌の世界のイノベーション企業ランクで十四位に入り、決算発表会でも三木谷氏は御満悦だった。だが、同誌We
b版の「気を付けろアマゾン、楽天とかいうのが参入してくるぞ」と題するコラムでは、痛烈な皮肉が書かれている。「楽天とイーベイツの組み合わせは、ECに革命を起こすだろう」という三木谷氏の言葉に対して「革命をもたらす? まさか。(中略)EC業界に必要なのはイノベーションではない。継続的なグローバリゼーションだ」「アマゾンは楽天の市場参入に特段恐れるべきだろうか。ハハハ、ノー」。これが、楽天に対する「世界の本音」である。
本業の限界を埋める金融部門
だが、海外事業以上に深刻なのは、国内の「楽天市場」にも暗雲が垂れ込めていることだ。
「(ソフトバンクの)孫さんのような(強気の)経営はできない。僕はどちらかと言うと堅実派だ」
三木谷氏はそう語っている。しかし、楽天の自己資本比率は一〇%を切っている。これはアグレッシブな財務戦略で知られるソフトバンクを下回る。楽天経済圏拡大のエンジンは、今やECではない。同社の事業は本業である「インターネットサービス」に加えて、「インターネット金融」「その他」と三事業があるが、事業別の営業利益(一三年度)は、インターネットサービスで四百七十五億円、インターネット金融は四百四十二億円と本業を凌駕しつつある。一四年一~九月で見ても、三百八十八億円と三百三十四億円である。
金融部門はカード、証券、銀行、生保、その他に分かれるが、なかでもカード(消費者金融)が大きい。楽天の成長エンジンは「誰でもつくれる」という評判の「楽天カード」である。EC事業での成長には限界が見え、同社では「ヨコテン(横展開)」と称してEC以外の事業で収益を確保しようとしている。
「サウンドハウスはこれまで三年間、楽天市場に商品を掲載しておりました。ところがこの度、楽天は一方的に弊社の決済口座としては楽天銀行の口座に一本化するということを決め、お客様に告知しました」
楽器販売のサウンドハウスは一四年十一月、リリースでこう発表した。「出店店舗の銀行口座を勝手に開設し、決済用口座としてはその口座しか認めないということは、これまでの日本の商習慣ではありえないことです」。これぞ楽天流。自社銀行の預金残高を増やすためなら、手段は選ばないのだ。
本業に関して言えば、楽天市場の出店数は一三年十二月をピークに減少を続けているという事実がある。これは初めてのことであり、明らかな転換点を迎えたと見ていい。成長モデルの終焉の兆しといえよう。「これからは数ではなく品質だ。相当数の出店申請を却下している」と三木谷氏は強調してみせる。「自分から断っている」と言いたいようだ。だが、楽天市場内で出店者同士の競争は激しく、高い出店料を払う店舗は既に疲弊し、店主たちは相次いで楽天を去っている。出店無料のヤフーショッピングが、楽天の後退に拍車をかける。さらには直販タイプの事業でも、同社は躓いた。
「楽天は、物流の素人ぶりを露呈してしまった」(業界筋)
日用品のスピード配送事業「楽天24」では、ヤフー傘下アスクルが運営するロハコやアマゾンに完敗し、バックエンドを支えるために一〇年三月に設立した楽天物流は、「設立半年で赤字に耐えきれずに撤退に追い込まれ、楽天が吸収合併することでもみ消した」(同前)のである。しまいには、この赤字の「楽天24」の事業を、一二年に買収した傘下のケンコーコムに押し付け、同社創業者である後藤玄利氏を退任に追い込んだ。
「偽装」は日常の風景
国内EC市場ですら、にわかに綻びが顕わになってきた。だがこれも、同社の社風を考えれば至極当然かもしれない。
「とてもいい商品で、びっくりしています。また利用したいと思います。」
これは、「めろん6969」という名前の楽天ユーザーが書いた様々な商品へのレビューである。八十件の商品に対して、この同じ文言でレビューが繰り返され、すべて一四年十二月十四日に投稿されている。こうした「サクラ」と思しき疑惑のレビューが、サイト内には恒常的に蔓延している。もはや「偽装」は、楽天市場の日常風景である。「閉店した店舗に、なぜか新しいレビューが次々と表示されていた」との証言を聞いても誰も驚かないだろう。楽天経済圏に蔓延る「疑惑」は枚挙にいとまがない。「電子書籍KOBOの強制無料プレゼント問題(端末普及率を水増し)」「KOBOの書籍出版点数水増し問題」「楽天スーパーセール二重価格表示問題」などは、周知の通りだ。あまり報道されなかったが、楽天銀行が「一週間円定期預金」で金利〇・五%という超高金利を六月二十三日に発表し、預金者を引き付けておいて同月二十九日に終了したという「高金利偽装疑惑」も発生した。消費者の目を眩ませる数々のトリックを弄する会社が、繁栄を続けることはない。
「ライブドアよりはだいぶマシだ」。六本木ヒルズ、森タワー十八階。十年ほど前に楽天本社を訪れた際の、筆者の率直な第一印象である。当時は堀江貴文氏の存在のおかげで、三木谷氏はまともな経営者であるかに見えた。それゆえ、同社の数々の無礼な振る舞いにも、日本社会は寛容に対応してきたのだ。
品川にある現在の楽天本社内には、「おもてなし」と書かれた同社のポスター、さらには三木谷氏の座右の銘「人は財なり」の書が飾ってある。「心にもないことを平気で言えるタイプ」(同社OB)ではないか。
カナダの電子書籍コボを買収して「電子書籍販売の課税逃れ」をする傍ら、政府の諮問機関「産業競争力会議」では、日本の未来について語っている。ただ、いくら綺麗事を並べても、本質はいつかは露見する。斜めに腰かけ、不敵な笑みを浮かべながら「おもてなしとは何か」を語る三木谷氏の姿が、虚飾に満ちた楽天の経営を如実に物語っている。
掲載物の無断転載・複製を禁じます©選択出版