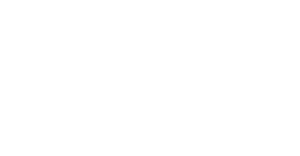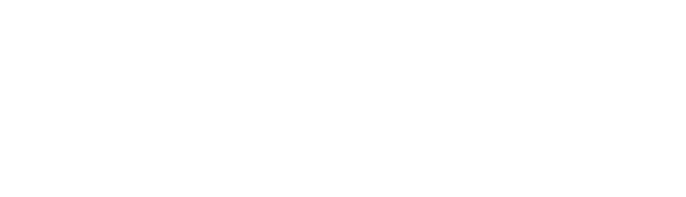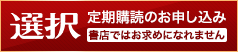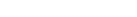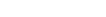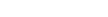中部電力も「再エネ撤退」の暴挙
鳥取・米子市を「喰い物」にした悪辣
2025年10月号公開
中部電力、東急不動産、三菱HCキャピタルなど大手企業が主導して、鳥取県米子市に建設したバイオマス発電所が爆発事故を起こした挙げ句に、勝手に廃業届を出し、地元で大顰蹙を買っている。再生可能エネルギーで実績をあげたい中部電が他電力管内にごり押し進出、地元自治体に用地斡旋、住民説得をさせたうえで、事故後は「収益が見込めない」と切り捨てた。地元は施設の撤去を求めているが、中部電らは完全無視の構えで、朽ちていく発電所を前に地元住民の怒りは爆発寸前だ。
無策の末の「大爆発」
白砂の浜に緑豊かな松林が延び、日本海と雄大な大山の山容を同時に眺めることのできる風光明媚な米子市の弓ヶ浜海岸。『ゲゲゲの鬼太郎』の作者、水木しげるの出身地で、鬼太郎や目玉おやじのオブジェが並ぶ境港は目と鼻の先だ。
多くの観光客が訪れる土地にまったく不釣り合いな米子バイオマス発電所が操業を開始したのは2022年4月のことだった。もともと地域の住民の多くは受け入れに反対だった。植物由来の燃料を使う、環境に優しい発電所という美辞麗句で説明されたが、現実は運転時のタービン騒音に加え、境港からの燃料搬入の大型トラックの交通量が増えることも懸念された。
それでも住民がしぶしぶ受け入れたのは、「出資者の顔ぶれが一流企業で、問題があれば誠実に対応しますという口約束があったからだ」と地元の有力者は語る。中部電、東急不動産、三菱HCキャピタル(三菱商事や三菱UFJ銀行などが出資)が各30%ずつを出資、残りはバイオマス発電のプロを自称するシンエネルギー開発(本社:群馬県沼田市)と地元資本の三光が各5%だった。
何といっても住民らを安心させたのは中部電が、東京電力、関西電力と並ぶ電力御三家の一角で、林欣吾社長が進出当時は電気事業連合会副会長(24年4月から会長)も務めるという事実だった。長年、地域独占を許され、地域との関係性を重視して来た電力会社がよもや地元を軽視することはないだろうという考えがあった。
加えて、地元自治体の鳥取県、米子市も誘致に積極姿勢で、米子市は中部電の代理人のように用地探しに奔走、弓ヶ浜の景勝地に決まった後も住民への説得を前面に立って進めた。騒音や事故リスクの高さなどバイオマス発電所に関する悪い情報は次第に忘れ去られ、地元経済への波及効果の大きさや地球温暖化対策への協力など業者が語る美しいストーリーが地元の人々の心を捉えていった。
米子バイオマス発電所は5万4500kWの発電能力を持ち、一般家庭なら12万5千軒分を賄えるという再生可能エネルギーとしては国内では大規模なものだった。燃料は木材の端材、間伐材などを加工して燃焼効率を高めた木質ペレットとアブラヤシの殻を粉砕してチップ化した「PKS」でいずれも東南アジアなどからの輸入だった。
22年4月に発電を開始すると、たちまち周辺住民から騒音の苦情が相次いだ。発電所と住宅街に騒音を軽減する十分な離隔がなかった。だが、住民にはより大きな問題が待ち構えていた。23年に入ると、発電所の燃料貯蔵所などで火災が月1回のようなペースで発生した。木質ペレットが水分を含んで発酵し、発生したメタンガスに引火したほか、燃料の微粒子による粉塵爆発も起きた。
中部電などがこうした危険性を認識していないはずはなかったが、抜本的な安全対策は取られないまま、発電を続け、収益最大化に邁進した。中部電などは「火災事故は小規模で、対策を強化したから問題ない」と米子市や地元住民に報告。火災事故が連続し、停止を求める声があがってからは、住民はもちろん行政側の貯蔵・搬送設備の改善要求を黙殺した。
「大山が噴火したかと思った」(地元住民)という大爆音と震動が周辺の住宅を襲ったのは23年9月9日の朝9時すぎだった。米子バイオマス発電所の基幹設備を収める建屋に燃料を搬入するエレベーターで大爆発が起き、建屋が半壊、発電機本体も重大な損傷を受けた。火災は約4時間続いた後にようやく消し止められたが、素人目にも復旧困難な大被害だった。
その時点で、発電所内には可燃性の高い木質ペレットなどが残っていたものの、会社側は住民への情報提供や避難措置などは行わず、見かねた米子市が安全対策の申し入れを行うほどの無軌道ぶりだった。発電所運転のプロのはずの中部電の脳天気な行動と無責任さは地元で激しい反発を招いた。
もともとバイオマス発電所の建設は中部電や東急不動産が地元に強く求め、実現したものだった。再生可能エネルギーの買い取り制度(FIT)によって高い利益率が見込め、株主や大口顧客に対しても地球温暖化対策への取り組みとしてアピールしやすいという下心があったのは確実だ。
だが、バイオマス発電所には引火・爆発事故のリスクがある。石狩新港、武豊、袖ケ浦、山形などこの数年でも国内のバイオマス発電所で火災、爆発事故が多数、起きている。事故のメカニズムはほぼ解明されているものの、安全対策を万全にすれば建設コストは倍増し、利益は出ない。「安全性より稼働率」という“悪の轍”に中部電は前のめりにはまったといえる。
撤去に応じず「放置」
事故を起こした米子バイオマス発電所は2年以上たった今もそのまま放置されている。中部電らは8月1日、中国経済産業局に同発電所の事業廃止届を提出した。地元への事前通告はなかった。「燃料や可燃物はすべて敷地外に撤去し、安全性は担保した」と中部電らは説明し、一件落着の構えだ。
だが、事故で半壊した建屋や燃料サイロは遠くからでも見えるため、地元住民は毎日、不安にさらされている。「設備の解体、撤去と更地にしての返還」を米子市や住民側が求めても、中部電は「一株主の立場で申し上げることはない」という無責任さ。「地方を見下す態度が露骨」と取材にあたった地元メディアの記者は批判する。爆発事故で鉄骨の構造はダメージを受けており、海風にさらされ、錆も出始めている。冬場の日本海の強風でいずれ崩壊しかねない、と地元は不安を隠さない。
10億円をくだらない、と言われる解体・撤去費用を惜しみ、5年、10年で自然に崩れ堕ちる日を待つ中部電にはかつて地域共生を掲げた公益事業者の姿はもはや微塵もない。
無策の末の「大爆発」
白砂の浜に緑豊かな松林が延び、日本海と雄大な大山の山容を同時に眺めることのできる風光明媚な米子市の弓ヶ浜海岸。『ゲゲゲの鬼太郎』の作者、水木しげるの出身地で、鬼太郎や目玉おやじのオブジェが並ぶ境港は目と鼻の先だ。
多くの観光客が訪れる土地にまったく不釣り合いな米子バイオマス発電所が操業を開始したのは2022年4月のことだった。もともと地域の住民の多くは受け入れに反対だった。植物由来の燃料を使う、環境に優しい発電所という美辞麗句で説明されたが、現実は運転時のタービン騒音に加え、境港からの燃料搬入の大型トラックの交通量が増えることも懸念された。
それでも住民がしぶしぶ受け入れたのは、「出資者の顔ぶれが一流企業で、問題があれば誠実に対応しますという口約束があったからだ」と地元の有力者は語る。中部電、東急不動産、三菱HCキャピタル(三菱商事や三菱UFJ銀行などが出資)が各30%ずつを出資、残りはバイオマス発電のプロを自称するシンエネルギー開発(本社:群馬県沼田市)と地元資本の三光が各5%だった。
何といっても住民らを安心させたのは中部電が、東京電力、関西電力と並ぶ電力御三家の一角で、林欣吾社長が進出当時は電気事業連合会副会長(24年4月から会長)も務めるという事実だった。長年、地域独占を許され、地域との関係性を重視して来た電力会社がよもや地元を軽視することはないだろうという考えがあった。
加えて、地元自治体の鳥取県、米子市も誘致に積極姿勢で、米子市は中部電の代理人のように用地探しに奔走、弓ヶ浜の景勝地に決まった後も住民への説得を前面に立って進めた。騒音や事故リスクの高さなどバイオマス発電所に関する悪い情報は次第に忘れ去られ、地元経済への波及効果の大きさや地球温暖化対策への協力など業者が語る美しいストーリーが地元の人々の心を捉えていった。
米子バイオマス発電所は5万4500kWの発電能力を持ち、一般家庭なら12万5千軒分を賄えるという再生可能エネルギーとしては国内では大規模なものだった。燃料は木材の端材、間伐材などを加工して燃焼効率を高めた木質ペレットとアブラヤシの殻を粉砕してチップ化した「PKS」でいずれも東南アジアなどからの輸入だった。
22年4月に発電を開始すると、たちまち周辺住民から騒音の苦情が相次いだ。発電所と住宅街に騒音を軽減する十分な離隔がなかった。だが、住民にはより大きな問題が待ち構えていた。23年に入ると、発電所の燃料貯蔵所などで火災が月1回のようなペースで発生した。木質ペレットが水分を含んで発酵し、発生したメタンガスに引火したほか、燃料の微粒子による粉塵爆発も起きた。
中部電などがこうした危険性を認識していないはずはなかったが、抜本的な安全対策は取られないまま、発電を続け、収益最大化に邁進した。中部電などは「火災事故は小規模で、対策を強化したから問題ない」と米子市や地元住民に報告。火災事故が連続し、停止を求める声があがってからは、住民はもちろん行政側の貯蔵・搬送設備の改善要求を黙殺した。
「大山が噴火したかと思った」(地元住民)という大爆音と震動が周辺の住宅を襲ったのは23年9月9日の朝9時すぎだった。米子バイオマス発電所の基幹設備を収める建屋に燃料を搬入するエレベーターで大爆発が起き、建屋が半壊、発電機本体も重大な損傷を受けた。火災は約4時間続いた後にようやく消し止められたが、素人目にも復旧困難な大被害だった。
その時点で、発電所内には可燃性の高い木質ペレットなどが残っていたものの、会社側は住民への情報提供や避難措置などは行わず、見かねた米子市が安全対策の申し入れを行うほどの無軌道ぶりだった。発電所運転のプロのはずの中部電の脳天気な行動と無責任さは地元で激しい反発を招いた。
もともとバイオマス発電所の建設は中部電や東急不動産が地元に強く求め、実現したものだった。再生可能エネルギーの買い取り制度(FIT)によって高い利益率が見込め、株主や大口顧客に対しても地球温暖化対策への取り組みとしてアピールしやすいという下心があったのは確実だ。
だが、バイオマス発電所には引火・爆発事故のリスクがある。石狩新港、武豊、袖ケ浦、山形などこの数年でも国内のバイオマス発電所で火災、爆発事故が多数、起きている。事故のメカニズムはほぼ解明されているものの、安全対策を万全にすれば建設コストは倍増し、利益は出ない。「安全性より稼働率」という“悪の轍”に中部電は前のめりにはまったといえる。
撤去に応じず「放置」
事故を起こした米子バイオマス発電所は2年以上たった今もそのまま放置されている。中部電らは8月1日、中国経済産業局に同発電所の事業廃止届を提出した。地元への事前通告はなかった。「燃料や可燃物はすべて敷地外に撤去し、安全性は担保した」と中部電らは説明し、一件落着の構えだ。
だが、事故で半壊した建屋や燃料サイロは遠くからでも見えるため、地元住民は毎日、不安にさらされている。「設備の解体、撤去と更地にしての返還」を米子市や住民側が求めても、中部電は「一株主の立場で申し上げることはない」という無責任さ。「地方を見下す態度が露骨」と取材にあたった地元メディアの記者は批判する。爆発事故で鉄骨の構造はダメージを受けており、海風にさらされ、錆も出始めている。冬場の日本海の強風でいずれ崩壊しかねない、と地元は不安を隠さない。
10億円をくだらない、と言われる解体・撤去費用を惜しみ、5年、10年で自然に崩れ堕ちる日を待つ中部電にはかつて地域共生を掲げた公益事業者の姿はもはや微塵もない。
掲載物の無断転載・複製を禁じます©選択出版