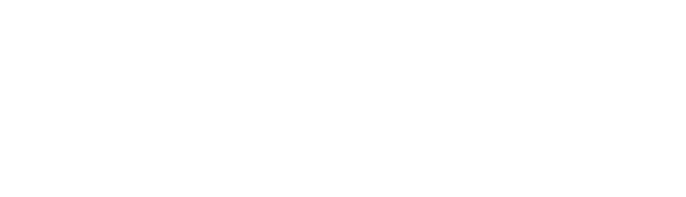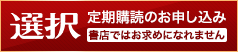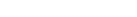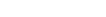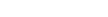「泥縄経営」に陥った武田薬品
新研究所建設にもすでに「疑問符」
2010年8月号公開
「凋落のキッカケになるのではないか」と心配する人もいれば、「体のいい研究者のリストラなのではないか」と口にする人もいる。武田薬品工業が一千億円強を投じて神奈川県の藤沢、鎌倉両市にまたがる旧湘南工場跡地に建設中の巨大研究所だ。人体に危険性のある微生物を扱う施設も備えることから、バイオハザードを引き起こす恐れがあると地元の市民団体らによる反対運動も起きている。しかし同社では、今年度中に完成させる予定を崩さない。
武田薬品が「強引」になるのもわけがある。新薬開発が喫緊の課題の同社にとって、新しい研究所の早期稼働と速やかな成功が求められているからだ。しかし、これが起死回生の策となると見る向きは少ない。むしろ後述するが、税金をつぎ込んだ末の壮大な無駄遣いに終わる可能性の方が内外から指摘されている。
後継新薬の「確保」に失敗
武田薬品が一九八八年にオープンしたばかりの茨城県のつくば研究所と、戦前から続く大阪市・十三の大阪工場・研究所を統合して、新たに研究所をつくると発表したのが二〇〇六年。これまではつくば研で薬の芽を見つけ、大阪研で薬に育てるという分担制を採ってきた。ところが、このスキームでは新薬は生まれなかった。
現在、新薬の開発成功確率は二万六千分の一程度にまで低下している。同社に限らず国内外の製薬各社は新薬の枯渇に苦しんでいる。その意味で武田薬品だけが拙かったともいえないのだが、そこは「信賞必罰」を徹底している同社。およそ二十年間にわたって成果を出せなかった両研究所の研究員に「お国替え」という罰を与えたのだと、ライバル社では見ている。
とはいえ、新研究所になれば新薬開発が進むという保証はない。この移転・統合計画を推進した長谷川閑史社長自身、確証などないはずだ。「創薬は、研究所を一カ所にまとめれば新薬が出るという単純なものではない」との疑問の声が同社の研究系社員の一部からも上がっている。新薬の研究は十~十五年の歳月が必要な気の長い仕事。環境の変化を嫌って異動を拒む研究員も多い。それを十分知った上での計画だけに、冒頭述べたように研究員の「偽装リストラ」との嫌疑すら持ち上がっているのである。
社内から疑問符で見られる新研究所の建設が武田薬品の自己責任で行われるのなら、失敗しても究極的には問題はない。しかしこの移転・統合計画には神奈川県から八十億円もの補助金が注ぎ込まれている。〇六年当時、二百億円の補助金を用意して府内残留を熱望した大阪府を蹴った長谷川社長の「決断」は大きな話題となったが、一方、棚ぼたに気を良くした松沢成文神奈川県知事がJR東日本に要請し、新研究所の近くの東海道線に新駅を作る動きもある。武田薬品にとって至れり尽くせりの待遇が用意されているのである。
この時、自治体の首長を大胆にも両天秤に掛けた長谷川社長であるが、製薬企業のトップとしての「実績」は思いのほか少ない。武田薬品は武田國男前会長がワンマン社長として君臨した時代、前立腺がん薬「リュープリン」が米国でバカ売れした。さらに抗潰瘍薬「タケプロン」、高血圧薬「ブロプレス」、糖尿病薬「アクトス」も大ヒットした。最盛期には四つのブロックバスター(年間一千億円以上を売り上げる大型新薬)が同社を支えるという幸運に恵まれた。当時の武田社長は「国際戦略四品目」と豪語したが、いずれも大阪研による大金星だった。しかし、これらの新薬のうちリュープリンとタケプロンはすでに特許が切れ、来年にはアクトスも特許満了を迎える。一二年にはブロプレスも特許保護期間が終了する。
社長報酬は二億二千万
米国では特許が切れると安い後発医薬品が一気に登場し、高い新薬は使われなくなる。ところが長谷川社長は国際戦略四品目の後継新薬の確保に「失敗」した。アクトスの後継品でDPP4阻害薬と呼ばれる糖尿病薬「ネシーナ」は日本では二月に承認されたものの、米国ではFDA(食品医薬品局)から追加試験を求められ承認が遅れている。なにより、DPP4阻害薬はメルクやノバルティスが先行発売しており武田薬品は三番手。苦戦が予想されている。
同様に、睡眠導入剤の「ロゼレム」も当初は「売れる」(長谷川社長)と胸を張っていたが、米国市場では見向きもされなかった。そこで「今後は低分子薬ではなく、抗体医薬。特に抗がん剤に力を入れる」(同)と宣言し、大腸がんを対象にした「ベクティビックス」を六月に国内向けに発売したが、ロシュの大ヒット新薬「アバスチン」の後塵を拝している。そもそも武田薬品の抗がん剤分野への進出は三年以上出遅れたと製薬業界ではいわれている。経営判断のミスを指摘されても致し方ない。
むろん、長谷川社長もじっとしていたわけではない。米バイオ医薬品メーカーのミレニアム・ファーマシューティカルズを八千九百億円の大枚を投じて買収したほか、創薬ベンチャーからも新薬候補化合物を盛んに導入した。しかし、登場したのはブロックバスターとは程遠い小粒な新薬だった。
偉大な経営者の「次」が期待を裏切るという現象は製薬業界に限った話ではないが、新薬の相次ぐ特許切れという最もリスキーな時に適したトップであったのか、疑問はぬぐえない。そもそも長谷川社長は武田前会長が意図した社長候補三人の中の二番手だった。前会長が最も期待していたのは鈴木伸隆常務だったが、不幸にも病死したため、米子会社勤務時代の後輩だった長谷川氏を社長に据えた。当然、武田前会長に逆らうことはしないが、日本人離れした歯に衣着せぬ物言いは前会長と同じで、この点でも両者の接近を促した。
新薬メーカーにとって生命線といえる研究所の「改革」は、本来は、慎重がうえにも慎重に進めなければならない施策だった。まして実績のある十三の大阪研の閉鎖などという荒療治は、計算できない副作用を伴うだけに好況時にこそ行うべきものでなかったか。
実際、「研究施設は静かな環境より雑然とした場所の方がよい」と断言する研究者は少なくない。「ノーベル賞受賞者がよく湯船の中で閃いたと言うように、傍目には自然に溢れたところで研究した方が捗ると考えがちだが、研究者も人間。退社後、飲み屋などで騒いでいるときにハッと気付いたりする。住宅街の中の研究所より繁華街がそばにある十三のほうが研究に向いている。近くに駅ができるといっても横浜まで行くわけにもいかない」(武田薬品社員)。
長谷川社長は今夏から公開を義務付けられた上場企業の役員報酬で二億二千万円と、製薬業界では日本人トップだった。だが、新研究所での新薬開発にも「失敗」すれば武田薬品は米国市場でのプレゼンスを失い、国内でもライバルに追いつかれる。しかもその時、研究所の再移転などという構想が持ち上がれば、せっかくの補助金も無駄になる。「やらずぼったくり」との謗りも免れまい。ブロプレスの特許切れまで時間は少ない。近い将来から振り返ってみて、武田薬品の研究所移転・統合は同社凋落の序章となりそうである。
掲載物の無断転載・複製を禁じます©選択出版