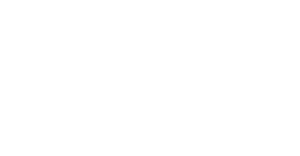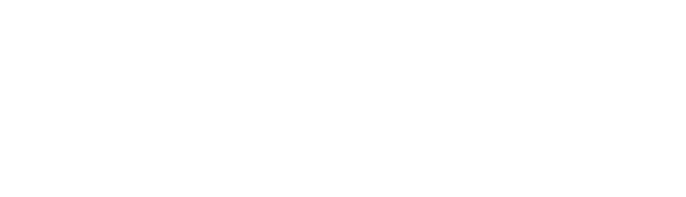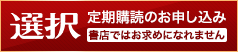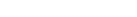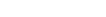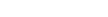住友商事「商社ドン尻」は末永く
兵頭体制で腐った「人事と社風」
2025年4月号公開
新年度を迎え、住友商事の少なからぬ幹部の間には強い危機感が渦巻く。
「2期連続の最下位も否めない。そのときは時価総額も突き放されるだろう」
妖魔のプロジェクト「アンバトビー」―。住商は2023年度、マダガスカルの世界最大級のニッケル開発事業に890億円の減損損失を計上、連結純利益を丸紅に抜かれ、5大商社の最下位に甘んじた。同事業の減損累計は1兆円に近く、すでに簿価はゼロ。社長の上野真吾は「売却も視野」として債務整理を進める一方、トラブル続きの操業の安定を図ってきた。
ところが、昨年9月、パイプラインが破損し、液状のニッケル鉱石が工場敷地外へ流出する事故が発生したのだ。売却どころか、またしても追加損失を余儀なくされる事態である。
住商の24年度純利益は5600億円の計画。丸紅のそれは5000億円だが、損失バッファー300億円が含まれ、上振れ余地がある。追加損失次第では再び丸紅の後塵を拝しかねない。
5大商社の中で唯一PBR(株価純資産倍率)1倍割れの住商の時価総額は4・4兆円に伸び悩み、すでに丸紅(4・2兆円)と拮抗しているのだ。
何より丸紅は4月、14人ごぼう抜きの新社長・大本昌之が就任した。55歳のトップ誕生に住商からは羨望の声が上がる。
「うちの社長より10歳若い。比べて60代半ば3人の集団指導体制では士気は上がらない」
スリートップの「延命策」
住商が1年前、会長・兵頭誠之、社長・上野、さらに新設の副会長に元副社長・南部智一が復帰し、同期入社扱いの同い歳3人がスリートップを独占したことは周知の通り。前社長の兵頭による独善的人事であり、「年齢より知見と判断力が重要」とされ、社長候補である当時の常務3人は退けられた。
兵頭悩乱の“お友達経営”と、社内外から揶揄されたのは言うまでもない。案の定、経営会議は同期3人が牛耳り、後輩役員たちが萎縮する異様な光景が続く。しかも、新年度4月1日付の役員人事をみた社員の失望は一段と高まった。
「和田常務をなぜ国内に封じ込めるのか」
社長候補は不動産の和田知徳、化学品の為田耕太郎、鉄鋼の本多之仁の1989年入社の3人。最右翼は米国法人社長の和田とみられていた。大阪大学大学院修了の一級建築士であり、英語も堪能、何より外連味がなく正論を吐く。経営刷新の輿望を担うその和田が専務に昇格したものの、関西支社長へ異動となったのだ。格上の米国法人社長を外された衝撃は大きい。
和田の後任に就いたのは為田である。経営企画部長の経験もあり、次期社長の本命に躍り出た格好だ。しかし、為田は温厚な半面、上司の意向を忖度するタイプ。乱世のトップには向かない。つまり個性の強い和田を外し、御しやすい為田を重用する人事はスリートップの延命策と解釈されているのだ。
「いや、為田常務さえ社長指名されるかは疑問。暗黒の6年になりかねない」
ある幹部は苦り切って指摘した。期せずして社長に就いた上野が早期に世代交代を進めようとしても、兵頭がそれを許さず、6年の会長任期一杯居座れば、89年組3人の社長の芽は消えるのだ。しかも、コーポレート部門には兵頭の腹心である副社長・清島隆之が陣取っている。
住商は新年度から執行役員の予備軍である「理事」を廃止し、「AP」と呼ばれる管理職に職制を一本化した。従来の理事は一定期間は同待遇のAP0にとどまるものの、実績を上げなければAP1、AP2へ降格される。これは清島肝煎りの人事制度であり、改悪を指摘する幹部は多かったが、ことごとく飛ばされた。その一方で恣意的な外部人材の登用が相次ぐ。
サステナビリティ担当常務・江田麻季子、人事担当執行役員・中澤佳子が典型例だろう。いずれも兵頭、清島がスカウトした外資企業出身の女性であり、いわば住商のジェンダーフリーを喧伝する広告塔だ。
しかし、実態は異なる。米タワーズぺリン出身の中澤など人事のプロの触れ込みだったが、スリートップに愛嬌を振りまくだけで期待外れ。事実上の辞任勧告と囁かれるロンドン駐在の辞令も意に介さず赴任する始末だ。降格もあり得る従来の理事の間に兵頭、清島への怨嗟が募るのは自然の成り行きだろう。
「理念先行」が招く最下位
「まず上位3社へ復帰を果たそうやないか」
上野は、ひと昔前の三菱商事、三井物産に次ぐ純利益3位への返り咲きを目指し、主力の鋼管に匹敵する「ナンバーワン事業群」の創出を掲げる。都市開発、再エネ、農業関連……、模索は続くが、肝腎の投資判断のプロセスが変わっていないのだ。
本部長への権限移譲は形式上進んでも、スリートップが牛耳る経営会議では事前に根回ししなければ投資承認は得られない。勢い案件は小粒となり、伊藤忠商事が筋悪のビッグモーターを買収したような逆張りの発想は出てこない。そんな体たらくでは伊藤忠を抜き返し、上位3社への復帰など夢のまた夢だ。
住商はどうして退嬰化してしまったのか―。別の幹部は、スリートップの微妙な人間関係を指摘する。
「兵頭社長の6年間は大型投資が1件もなかった。おそらく会長は同期2人に違和感を抱いてきたのだろう」
上野も南部も鉄鋼畑の出身であり、長く衆目が一致する将来の社長はドル箱の鋼管のエース南部だった。電力インフラ一筋の兵頭はその陰に隠れてきたが、兵頭にすれば、鋼管販売はしょせん住友金属工業(現日本製鉄)の“御用聞き”にすぎない。比べて発電所の建設・運営は現地の国富に直結し、技術、燃料、金融などの知見が求められるインテリジェンスの高い事業という自負があったに違いない。
それが、兵頭をして市況商品の大型投資を忌避させ、環境対策や女性登用などサステナビリティの理念に異常に傾斜した背景ではなかったか―。実はアンバトビープロジェクトも理念先行の負の遺産なのだ。
ニッケル工場はマダガスカルの紙幣にも描かれる国富の象徴。2005年当時、投資を決断したのは鉄鋼畑の独裁的社長・岡素之だったが、「短期的な損益であの国を捨てられるか!」という妄言が呪縛となり、兵頭らは撤退の時機を逸し、減損1兆円の深みにはまったのだ。
いずれにせよ、退嬰化した住商にもはや“逆命利君”の伝統的美風はない。誰も責任を取らない集団指導体制の廃止、それが最下位商社を免れる唯一の道にほかならない。(敬称略)
「2期連続の最下位も否めない。そのときは時価総額も突き放されるだろう」
妖魔のプロジェクト「アンバトビー」―。住商は2023年度、マダガスカルの世界最大級のニッケル開発事業に890億円の減損損失を計上、連結純利益を丸紅に抜かれ、5大商社の最下位に甘んじた。同事業の減損累計は1兆円に近く、すでに簿価はゼロ。社長の上野真吾は「売却も視野」として債務整理を進める一方、トラブル続きの操業の安定を図ってきた。
ところが、昨年9月、パイプラインが破損し、液状のニッケル鉱石が工場敷地外へ流出する事故が発生したのだ。売却どころか、またしても追加損失を余儀なくされる事態である。
住商の24年度純利益は5600億円の計画。丸紅のそれは5000億円だが、損失バッファー300億円が含まれ、上振れ余地がある。追加損失次第では再び丸紅の後塵を拝しかねない。
5大商社の中で唯一PBR(株価純資産倍率)1倍割れの住商の時価総額は4・4兆円に伸び悩み、すでに丸紅(4・2兆円)と拮抗しているのだ。
何より丸紅は4月、14人ごぼう抜きの新社長・大本昌之が就任した。55歳のトップ誕生に住商からは羨望の声が上がる。
「うちの社長より10歳若い。比べて60代半ば3人の集団指導体制では士気は上がらない」
スリートップの「延命策」
住商が1年前、会長・兵頭誠之、社長・上野、さらに新設の副会長に元副社長・南部智一が復帰し、同期入社扱いの同い歳3人がスリートップを独占したことは周知の通り。前社長の兵頭による独善的人事であり、「年齢より知見と判断力が重要」とされ、社長候補である当時の常務3人は退けられた。
兵頭悩乱の“お友達経営”と、社内外から揶揄されたのは言うまでもない。案の定、経営会議は同期3人が牛耳り、後輩役員たちが萎縮する異様な光景が続く。しかも、新年度4月1日付の役員人事をみた社員の失望は一段と高まった。
「和田常務をなぜ国内に封じ込めるのか」
社長候補は不動産の和田知徳、化学品の為田耕太郎、鉄鋼の本多之仁の1989年入社の3人。最右翼は米国法人社長の和田とみられていた。大阪大学大学院修了の一級建築士であり、英語も堪能、何より外連味がなく正論を吐く。経営刷新の輿望を担うその和田が専務に昇格したものの、関西支社長へ異動となったのだ。格上の米国法人社長を外された衝撃は大きい。
和田の後任に就いたのは為田である。経営企画部長の経験もあり、次期社長の本命に躍り出た格好だ。しかし、為田は温厚な半面、上司の意向を忖度するタイプ。乱世のトップには向かない。つまり個性の強い和田を外し、御しやすい為田を重用する人事はスリートップの延命策と解釈されているのだ。
「いや、為田常務さえ社長指名されるかは疑問。暗黒の6年になりかねない」
ある幹部は苦り切って指摘した。期せずして社長に就いた上野が早期に世代交代を進めようとしても、兵頭がそれを許さず、6年の会長任期一杯居座れば、89年組3人の社長の芽は消えるのだ。しかも、コーポレート部門には兵頭の腹心である副社長・清島隆之が陣取っている。
住商は新年度から執行役員の予備軍である「理事」を廃止し、「AP」と呼ばれる管理職に職制を一本化した。従来の理事は一定期間は同待遇のAP0にとどまるものの、実績を上げなければAP1、AP2へ降格される。これは清島肝煎りの人事制度であり、改悪を指摘する幹部は多かったが、ことごとく飛ばされた。その一方で恣意的な外部人材の登用が相次ぐ。
サステナビリティ担当常務・江田麻季子、人事担当執行役員・中澤佳子が典型例だろう。いずれも兵頭、清島がスカウトした外資企業出身の女性であり、いわば住商のジェンダーフリーを喧伝する広告塔だ。
しかし、実態は異なる。米タワーズぺリン出身の中澤など人事のプロの触れ込みだったが、スリートップに愛嬌を振りまくだけで期待外れ。事実上の辞任勧告と囁かれるロンドン駐在の辞令も意に介さず赴任する始末だ。降格もあり得る従来の理事の間に兵頭、清島への怨嗟が募るのは自然の成り行きだろう。
「理念先行」が招く最下位
「まず上位3社へ復帰を果たそうやないか」
上野は、ひと昔前の三菱商事、三井物産に次ぐ純利益3位への返り咲きを目指し、主力の鋼管に匹敵する「ナンバーワン事業群」の創出を掲げる。都市開発、再エネ、農業関連……、模索は続くが、肝腎の投資判断のプロセスが変わっていないのだ。
本部長への権限移譲は形式上進んでも、スリートップが牛耳る経営会議では事前に根回ししなければ投資承認は得られない。勢い案件は小粒となり、伊藤忠商事が筋悪のビッグモーターを買収したような逆張りの発想は出てこない。そんな体たらくでは伊藤忠を抜き返し、上位3社への復帰など夢のまた夢だ。
住商はどうして退嬰化してしまったのか―。別の幹部は、スリートップの微妙な人間関係を指摘する。
「兵頭社長の6年間は大型投資が1件もなかった。おそらく会長は同期2人に違和感を抱いてきたのだろう」
上野も南部も鉄鋼畑の出身であり、長く衆目が一致する将来の社長はドル箱の鋼管のエース南部だった。電力インフラ一筋の兵頭はその陰に隠れてきたが、兵頭にすれば、鋼管販売はしょせん住友金属工業(現日本製鉄)の“御用聞き”にすぎない。比べて発電所の建設・運営は現地の国富に直結し、技術、燃料、金融などの知見が求められるインテリジェンスの高い事業という自負があったに違いない。
それが、兵頭をして市況商品の大型投資を忌避させ、環境対策や女性登用などサステナビリティの理念に異常に傾斜した背景ではなかったか―。実はアンバトビープロジェクトも理念先行の負の遺産なのだ。
ニッケル工場はマダガスカルの紙幣にも描かれる国富の象徴。2005年当時、投資を決断したのは鉄鋼畑の独裁的社長・岡素之だったが、「短期的な損益であの国を捨てられるか!」という妄言が呪縛となり、兵頭らは撤退の時機を逸し、減損1兆円の深みにはまったのだ。
いずれにせよ、退嬰化した住商にもはや“逆命利君”の伝統的美風はない。誰も責任を取らない集団指導体制の廃止、それが最下位商社を免れる唯一の道にほかならない。(敬称略)
掲載物の無断転載・複製を禁じます©選択出版