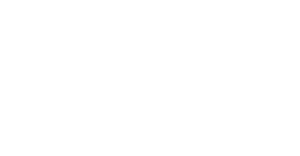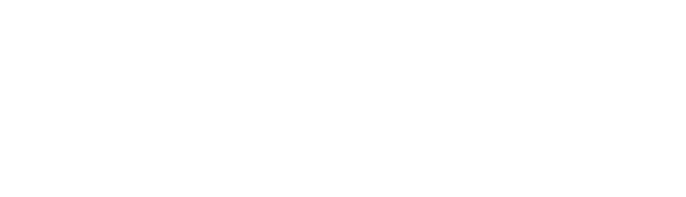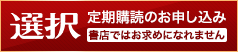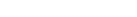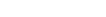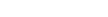日本車が中国に「完敗」する日
トヨタがBYDに負けた「技術力」
2025年8月号公開
日本の自動車業界でまさかの事態が起きている。「お家芸」だったはずのガソリンエンジン(以下、エンジン)の開発で、日本メーカーが中国メーカーの猛追を許しているのだ。技術力で日本メーカーに肉迫しつつあり、一部ではトヨタ自動車やホンダを超える性能を見せている。自動車業界に詳しいアナリストは「驚異的な追い上げだ。このまま手をこまぬいていると、EV(電気自動車)と同じようにエンジン車でも日本勢は中国勢の後塵を拝しかねない」と警鐘を鳴らす。
これまで日本メーカーは「中国メーカーはエンジン開発で日本メーカーに太刀打ちできない。だから、EVの開発にシフトした」(トヨタの社員)と高をくくってきた。高精度なエンジン部品を開発する知見も製造する技術も中国にはない。そこで、構造がシンプルで簡単に造れる上に、日本が手薄なEVに中国は活路を見いだしたのだと、まことしやかに語ってきた。ところが、その見方は的外れだったことが今、露呈している。
エンジンの性能を決する最も重要な指標に最大熱効率がある。この値が高いほど、燃費や環境性能に優れたエンジンということになる。例えば、トヨタが今年5月に発表した新型「RAV4」に搭載するエンジンの最大熱効率は41%程度だ。これが現在の日本車の実力値と見られている。
これに対し、中国最大の自動車メーカーに上り詰めた比亜迪(BYD)は最大熱効率が46・06%のエンジンを開発し、プラグインハイブリッド車に搭載して販売している。BYDだけではない。上海汽車集団や吉利汽車控股も46%超のエンジンの開発に成功している。最大熱効率は1ポイント高めるのに年単位の開発リソースが必要とも言われる。その難易度の高い開発において、日本メーカーを尻目に中国メーカー同士で世界一を競い合っているというのが現実だ。
「EVファースト」の妄信
電池メーカーだったBYDが自動車事業を手掛けてから20年あまりしか経っていない。にもかかわらず、なぜここまで技術力を高められたのか。これは日欧のメーカーによる「EVシフト」の妄信に理由がある。
2015年に独フォルクスワーゲンが起こしたディーゼルエンジン不正問題「ディーゼルゲート」を契機に、欧州はEVシフトに舵を切った。その後、欧州連合(EU)による脱炭素政策の強化でEVシフトを加速させる一方、欧州メーカーは軒並みエンジン開発の縮小を宣言した。「新型エンジンの開発を中止し、EV開発にリソースを集約する」(独ダイムラー)と、多くのメーカーが判で押したかのように言い出したのだ。
これにより、欧州メーカーから多くのエンジン技術者が中国メーカーに転じたと言われている。技術は人に付いていく。こうして先端技術が中国メーカーのエンジン開発現場に流入し、最大熱効率の飛躍的な向上として現れたというわけだ。
その証拠に、中国メーカーが最大熱効率を高めるために採用した技術─圧縮比の向上、タンブル流の強化、ロングストローク化、排出ガス循環率の向上─は、欧州メーカーが使っているものと変わらない。「主にドイツメーカーのエンジン技術が中国メーカーに流れ込んだ」(ホンダの社員)と見られている。
EVシフトで方針転換したのは日本メーカーも同様だ。ホンダは40年を目標に「脱エンジン」を宣言。EV開発の人材を厚くする一方で、55歳以上を対象に早期退職制度を実施。これにより、相当数のエンジン技術者がホンダを去ったと見られている。エンジン車からEVまで全方位で開発すると強調していたトヨタも、一時は社内でEVファーストを打ち出し、エンジン開発からEV開発へ多くの技術者を異動させた。世界中のEV失速を目の当たりにし、最近になってようやく技術者をエンジン開発に戻している。こうした日本メーカーの失策の裏で、中国メーカーはしたたかにエンジン開発力を磨き続けていたというわけだ。
日本メーカーの中には「あくまでも最大熱効率に絞った数字。総合力ではまだまだ我々の方が上」(トヨタの社員)という声もある。確かに、エンジンの性能は最大熱効率だけではない。エンジンは走行中に回転数とトルクが様々に変化する。そのため、実用域全体で低燃費になるようにエンジンを開発するのが、日本メーカーの主流を成す考えだ。
だが、こうした意見を「負け惜しみに聞こえる」と前出のアナリストは断じる。中国の自動車産業が本格的に立ち上がって、まだ年数が浅い。そんな新参者に、日本メーカーが「エンジンの代表性能で先行を許した現実を直視すべきだ。既に中国メーカーはEVや自動運転の開発で日本メーカーを凌駕している。技術進化の速さを忘れてはならない」(前出アナリスト)。
日本部品メーカーの危機
エンジン開発の手を緩めた影響を自動車メーカー以上に被る恐れがあるのは、日本の部品メーカーだ。
中国の自動車メーカーはエンジンの開発力を高めるとともに、現地における部品のサプライチェーンの確立に努めてきた。その結果、高性能なエンジン開発を支える部品を造る上で必須の高度な技術(高精度な加工や接合、表面処理など)をものにした部品メーカーが中国に増えてきた。
しかも、驚くべきはその価格競争力だ。価格は日本の部品メーカーの7割程度、半値のケースも珍しくない。おまけに、スピードでも中国の部品メーカーに軍配が上がる。開発期間は日本の部品メーカーのざっと2分の1といったところだ。
つまり、今や中国の部品メーカーは日本の部品メーカーに性能で追い付き、コスト競争力と開発スピードで圧倒しているのだ。確かに、耐久性を含めた品質面では日本の部品メーカーに一日の長があるが、それも早晩、追い付かれる可能性は高い。
このままでは日本の部品メーカーは受注量が減る可能性がある。既にその兆候は出ている。中国の自動車メーカーの多くが「部品の発注先リストに日本メーカーはない」と言うからだ。現地メーカーから安く早く手に入る部品を、わざわざ他から買う理由が見つからないというのである。このまま日本の自動車メーカーがエンジン開発で中国勢に完敗するようなことがあれば、日本の部品メーカーの大半は間違いなく沈む。
これまで日本メーカーは「中国メーカーはエンジン開発で日本メーカーに太刀打ちできない。だから、EVの開発にシフトした」(トヨタの社員)と高をくくってきた。高精度なエンジン部品を開発する知見も製造する技術も中国にはない。そこで、構造がシンプルで簡単に造れる上に、日本が手薄なEVに中国は活路を見いだしたのだと、まことしやかに語ってきた。ところが、その見方は的外れだったことが今、露呈している。
エンジンの性能を決する最も重要な指標に最大熱効率がある。この値が高いほど、燃費や環境性能に優れたエンジンということになる。例えば、トヨタが今年5月に発表した新型「RAV4」に搭載するエンジンの最大熱効率は41%程度だ。これが現在の日本車の実力値と見られている。
これに対し、中国最大の自動車メーカーに上り詰めた比亜迪(BYD)は最大熱効率が46・06%のエンジンを開発し、プラグインハイブリッド車に搭載して販売している。BYDだけではない。上海汽車集団や吉利汽車控股も46%超のエンジンの開発に成功している。最大熱効率は1ポイント高めるのに年単位の開発リソースが必要とも言われる。その難易度の高い開発において、日本メーカーを尻目に中国メーカー同士で世界一を競い合っているというのが現実だ。
「EVファースト」の妄信
電池メーカーだったBYDが自動車事業を手掛けてから20年あまりしか経っていない。にもかかわらず、なぜここまで技術力を高められたのか。これは日欧のメーカーによる「EVシフト」の妄信に理由がある。
2015年に独フォルクスワーゲンが起こしたディーゼルエンジン不正問題「ディーゼルゲート」を契機に、欧州はEVシフトに舵を切った。その後、欧州連合(EU)による脱炭素政策の強化でEVシフトを加速させる一方、欧州メーカーは軒並みエンジン開発の縮小を宣言した。「新型エンジンの開発を中止し、EV開発にリソースを集約する」(独ダイムラー)と、多くのメーカーが判で押したかのように言い出したのだ。
これにより、欧州メーカーから多くのエンジン技術者が中国メーカーに転じたと言われている。技術は人に付いていく。こうして先端技術が中国メーカーのエンジン開発現場に流入し、最大熱効率の飛躍的な向上として現れたというわけだ。
その証拠に、中国メーカーが最大熱効率を高めるために採用した技術─圧縮比の向上、タンブル流の強化、ロングストローク化、排出ガス循環率の向上─は、欧州メーカーが使っているものと変わらない。「主にドイツメーカーのエンジン技術が中国メーカーに流れ込んだ」(ホンダの社員)と見られている。
EVシフトで方針転換したのは日本メーカーも同様だ。ホンダは40年を目標に「脱エンジン」を宣言。EV開発の人材を厚くする一方で、55歳以上を対象に早期退職制度を実施。これにより、相当数のエンジン技術者がホンダを去ったと見られている。エンジン車からEVまで全方位で開発すると強調していたトヨタも、一時は社内でEVファーストを打ち出し、エンジン開発からEV開発へ多くの技術者を異動させた。世界中のEV失速を目の当たりにし、最近になってようやく技術者をエンジン開発に戻している。こうした日本メーカーの失策の裏で、中国メーカーはしたたかにエンジン開発力を磨き続けていたというわけだ。
日本メーカーの中には「あくまでも最大熱効率に絞った数字。総合力ではまだまだ我々の方が上」(トヨタの社員)という声もある。確かに、エンジンの性能は最大熱効率だけではない。エンジンは走行中に回転数とトルクが様々に変化する。そのため、実用域全体で低燃費になるようにエンジンを開発するのが、日本メーカーの主流を成す考えだ。
だが、こうした意見を「負け惜しみに聞こえる」と前出のアナリストは断じる。中国の自動車産業が本格的に立ち上がって、まだ年数が浅い。そんな新参者に、日本メーカーが「エンジンの代表性能で先行を許した現実を直視すべきだ。既に中国メーカーはEVや自動運転の開発で日本メーカーを凌駕している。技術進化の速さを忘れてはならない」(前出アナリスト)。
日本部品メーカーの危機
エンジン開発の手を緩めた影響を自動車メーカー以上に被る恐れがあるのは、日本の部品メーカーだ。
中国の自動車メーカーはエンジンの開発力を高めるとともに、現地における部品のサプライチェーンの確立に努めてきた。その結果、高性能なエンジン開発を支える部品を造る上で必須の高度な技術(高精度な加工や接合、表面処理など)をものにした部品メーカーが中国に増えてきた。
しかも、驚くべきはその価格競争力だ。価格は日本の部品メーカーの7割程度、半値のケースも珍しくない。おまけに、スピードでも中国の部品メーカーに軍配が上がる。開発期間は日本の部品メーカーのざっと2分の1といったところだ。
つまり、今や中国の部品メーカーは日本の部品メーカーに性能で追い付き、コスト競争力と開発スピードで圧倒しているのだ。確かに、耐久性を含めた品質面では日本の部品メーカーに一日の長があるが、それも早晩、追い付かれる可能性は高い。
このままでは日本の部品メーカーは受注量が減る可能性がある。既にその兆候は出ている。中国の自動車メーカーの多くが「部品の発注先リストに日本メーカーはない」と言うからだ。現地メーカーから安く早く手に入る部品を、わざわざ他から買う理由が見つからないというのである。このまま日本の自動車メーカーがエンジン開発で中国勢に完敗するようなことがあれば、日本の部品メーカーの大半は間違いなく沈む。
掲載物の無断転載・複製を禁じます©選択出版